
97全日本スーパーバイクチャンピオン、芳賀紀行。
今年の彼を表して、「圧倒的な強さ」という言葉が何度使われただろう。
芳賀紀行という人間像そのものを表現しているかのように、繰り返し使われたこの言葉。
確かに我々の目に見えてくるのは、強気なレース運びとハードなライディングだが、
22歳の青年としての芳賀紀行は、決して「圧倒的に強い」人物ではない。
2号にわたり、あまり語られてこなかった芳賀紀行の素顔に迫る。
【前編】
■ヤマハ発動機発行「WAY」1997年12月号掲載・1997年11月取材
サーキットの紀行
脱衣場のテーブルを囲んで、全員が腰を下ろした。父と母、そして祖父と兄の健輔が並び、二組のペアを作っている。芳賀紀行だけが僕の正面に、ひとりで座っている。背もたれのない丸椅子に膝を抱えているその様子はいかにも所在なげだ。そして硬く、こちらを突き放すような表情は、場所が紀行の実家の銭湯であっても、3日前に菅生で見たのとまったく変わらなかった。
今年、僕はサーキットに4回足を運んだ。全日本ロードレースは、第4戦鈴鹿と第5戦富士。4月の世界選手権ロードレース日本GP。そして7月の鈴鹿8耐。ヤマハのファクトリーライダーたちとは一通り言葉を交わしたが、芳賀紀行とだけは一度も話をしたことがなかった。仕事の流れでたまたまそうなったということもあるが、何となく話しかけにくい人だと、まず僕の方で身構えていた。
ピリピリしている、というわけではない。むしろリラックスして過ごしているシーンの方が記憶に残っている。特にチームメイトの吉川和多留やメカニック、それにライバルチームのライダーたちとふざけあっている姿をよく見かけた。
しかし何だか近寄りがたい。くつろいでいる時はくつろいでいる時で、話しかけんなよ、という空気を発散している。それは不快な空気ではない。だが、威圧感がある。それを本人が意識しているかどうかは分からなかったが、僕は紀行に対してそんな印象を持っていた。
弟、ということで勝手に膨らんだイメージもあって、やんちゃできかん坊、人のことなんか気にしない、オレはオレの道をいく……。そんな人のように思っていた。
吉川和多留、中野真矢、そして藤原儀彦、阿部典史。それに紀行の兄、健輔にはそんな感じをあまり受けない。彼らヤマハのファクトリーラーダーたちは、むしろ親しみやすい部類に入るレーサーだ。
例えば健輔は、レース直前などはかなり深いところに入り込み、集中力を高めるタイプだ。レース直前の健輔は、まるで祈るかのように手を組んで目を閉じ、集中力を高める。何者をも近づけない迫力がある。ピットクルーたちの声も、集中する健輔に気圧されるかのようにひそやかだ。とても話しかけられるような状態ではない。しかしそれ以外の場面で、タイミングさえ合えば、近寄りがたいという印象は健輔にはないのだ。
紀行と同じチームの吉川に至っては、いつ話しかけてはいけないのか分からないほどだ。レースを終えヘルメットを脱ぎ、まだ顔が紅潮しているような時でさえ、気軽に話しかけられそうに感じる。
5回目となるサーキット、菅生での全日本ロードレース選手権最終戦に、僕は紀行に会うためだけに行った。圧倒的な強さを見せつけながら全日本スーパーバイクのチャンピオンとなった芳賀紀行。未だ話したことのないぶん、彼がどんな人間なのか興味があった。
スーパーバイクの決勝レースは、スタートで飛び出した紀行がトップを走る。しかし、5周目のシケインで後続にクラッシュが発生し、赤旗中断した。マシンがピットインしてくる。
マシンを降りヘルメットを脱ぐと、紀行はディレクターズチェアにどかっと腰を下ろし、両足を投げ出した。呆然としたような表情で、動かない。目は一点を見つめたままだ。
一方の吉川は、座ることなくピットの中をうろうろと歩き回り、「オレも転びそうになったよ、あそこぉ」などと紀行に話しかけたり、鼻をかんだりしている。この日の吉川はちょっと風邪気味だった。
GP500に参戦している阿部典史が、紙コップのコーヒーを片手にピットを訪れる。紀行に軽く何事か話しかけたようだが、彼はあまり反応しない。呆然とした表情は変わらない。
つっと紀行が立ち上がったかと思うと、ピット2階のトイレに入る。戻ってくるとツナギの上半身だけ脱ぎ、またチェアに座って動かない。
でも、彼をずっと眺めていて、ひとつ気が付いた。彼の目は1点を見つめているようでいて、実際には視野の端で、ピット内の人の動きを注意深く観察しているようなのだ。スタッフが何をしているか、きちんと見ている。意外だった。
やがてスタート前進行が始まった。ツナギを着込み、シコを踏むようにぐんとしゃがむと、「うあーっ!」と一声、吠えた。
再スタート後の紀行は、吉川と藤原克昭に追いあげられながらもトップを走っていたが、周回遅れと接触して転倒し、そのままリタイヤした。今年、最初で最後のリタイヤだった。
肩を傷めた紀行は、右手を吊ってピットに戻ってきたが、猛烈な勢いで弁当を食べ尽くすと、カップラーメンをすすった。この日ダブルエントリーしていたGP500への出場は不可能だった。
ピットクルーへの留意という一面を発見したものの、紀行への話しかけにくさは変わらなかった。ちょっと言葉を交わしたが、言葉遣いこそていねいながら、その目は、何だろうこいつはという表情を隠すことがなかった。
とりあえず僕は、周辺の言葉の中から芳賀紀行という人間をつかむことにした。
今年ファクトリー入りし、250ccクラスを戦った中野真矢は、紀行についてこう語った。
「とにかく勢いがあって、元気なんです。レースの時、宿がたいてい一緒なんですけど、夜はプロレスごっこするんです。いたずらっ子みたいなとこもあって、トラックに閉じこめられたりもしましたよ」
じゃ、走りの雰囲気そのままだ。
「そう。でも、ああ見えても結構細かいところがあるんですよね。ドリンクの作り方の手順にもこだわりがあるみたいだし、マシンセッティングの煮詰め方も細かい。意外と神経質で、僕とは全然違いますね。僕は、いいかげんでスボラだから」
4月の日本GP以来の地元レースとなる阿部典史は、とてもリラックスしていた。しかし去年このレースで転倒し、鎖骨を骨折した経験があるため、勝ちたいけど転びたくない、と言った。
紀行について尋ねると、何度も、オレと芳賀くんとは違う、と繰り返した。
「ミニバイクの頃から知り合いなんですよ。中1か、中2ぐらいだったと思うんだけど。あんまり話したことないけど、オレとはタイプが違いますね」
どんな所が?
「うーん、何て言えばいいのかなぁ。難しいな。見た目の通り違うんですよ。僕は酒飲まないけど芳賀くんは飲むし、僕はトレーニングするけど芳賀くんはトレーニングやってないみたいで、そういうところも違いますね。それがいいとか悪いとかいうことじゃなくて、オレとは違う。ライディングはよく見たことがないから分かんないけど、500に乗っても速いですよね。オレ、スーパーバイクはあんまりうまく乗れないけど、彼は500を乗りこなせる。勢いがすごくあって、うらやましいっすよ」
世界で戦ってる立場から見て、来年紀行はワールドで通用すると思う?
「今、超乗れてるじゃないですか。だから勝てると思いますよ。僕は世界の壁を感じたけど、彼は感じなさそうな気がする」
プライベートで一緒に過ごすことは?
「ないですねぇ。彼、名古屋でしょう? 家が離れてるから……」
阿部はGP500の決勝レースで、「やっぱり熱くなった」と、転倒してしまうのだが、今回は大きなケガはなかった。
チームメイトとして一番近くで紀行を見ていた吉川。'94年、全日本スーパーバイクの初代チャンピオンとなった彼は、先輩風を吹かさないようにしてるんだけど、と言いながらも、やはり7歳年下の紀行には弟に対するような心配があったようだ。
「かなりナイーブで繊細なんですよ。私生活なんかでもちょっと変なことがあると、シュンとしちゃうとこがある。ピットでも、周りの雰囲気が効いちゃうタイプですよね。本人が気付いてんのか気付いてないのか分かんないけど、何かあったときに周りの精神的なサポートが必要なんです。難波(恭司)さんとか藤原(儀彦)さんとか、結構気を遣ってるとこもありますからね」
でも、ピットなんかでは結構リラックスしてるように見えてた……。よくふざけてたし。
「ああやって騒ぎながら、自分を盛り上げてるんですよ。だからワールドではちょっと心配な面 もありますね。言葉も英語になっちゃうしね。今までみたいに追う立場から、全日本チャンピオンっていう看板を下げて追われる立場になるわけだし。でも、若さもあるし、とにかく勢いがあるから、僕が乗り越えられなかった壁を彼なら乗り越えてくれると思う」
チームメイトとは言っても、やっぱりライバルでしょう? チャンピオンを取られて、悔しかった?
「いや、自分が自分の走りをできなかったからね。自分には自分の問題があった。それにヤマハトータルとして考えれば、よかったと思う」
オフには一緒に過ごしたり?
「僕、八王子なんですよ、住んでるのが。彼は名古屋だから、そんなにはね。でも、一緒にモトクロス行ったり、バーベキューしたり、テニスやゴルフに行ったりすることもある」
この日の最終レース、GP500の表彰台には、マイケル・ドゥーハン、岡田忠之、そして藤原儀彦が上がった。遠巻きに眺めていた紀行は、一緒にいるメカニックたちと「オーバーサーティーズだな」とニヤニヤしている。藤原と目が合った紀行は、「オヤジー!」と叫んだ。
レースがすべて終わり、スーパーバイクのチャンピオンとして年間表彰を受けた紀行は、右手を吊りながら表彰台の頂点に上がり、今日のレースはチャンピオンとった後のレースとしては最悪です、と言った。
来年は、世界ですね? と聞くアナウンサーの質問に対して、一呼吸置いた紀行は、
「あそこの白髪頭の人に聞かないと分かんないです」と、ヤマハ全日本ロードレースチーム監督の高津弘一を指した。この時紀行のワールド行きはほぼ内定していたが、正式にリリースされたのはその5日後、11月7日のことだ。
白髪頭呼ばわりされた高津は、紀行のレーサーとしての素質を高く評価している。
「ファクトリー入りする前は、神経質なとこがあると言われてたけど、ファクトリーになってからの走りはそんなことを感じさせなかったですね。度胸もあるし、レース中の駆け引きも優れてるし、今年は本当にチャンピオンにふさわしかったんじゃないですか。テストでも一番時計じゃないと納得しないところがあって、いつでもベストを尽くすんですよね。レーサーとしては素晴らしいことだと思う」
レース中はピリピリする方ですか、紀行選手は?
「いや、レースをやるのは、勝ちたいという気持ちがもちろん強くあるんだけど、一方で楽しみたい気持ちもあるようですね。だからスタッフやエンジニアをすごく大事にするし、思いやりもありますね」
ワールドでの課題は?
「今の走りはワールドでも十分に通用すると思いますね。あとはコースに早く慣れることぐらいでしょう。グリップレベルの低いコースとか、いろいろあるからね」
レーサーとしてではなく、ひとりの若者として芳賀紀行をどう見ていますか?
「レース終わったら名古屋に帰っちゃうから、プライベートのところは分かんないけどね。まぁ海外テストに行くと空港や街の中でブランドショップをよく回ってるみたいですよ。イヤリングしてみたり、ブレスレットしてたり、髪を染めて、何て言うんだ、そう、茶髪にしてみたりね」
そういうの、高津さんの目から見るとどんな風に?
「そんなには気になんないですね。まぁ、今日日の若者であるってことじゃないですかね。でも、マジメですよ。ファクトリーライダーとしての自覚もあるしね。何かあれば、みんなに迷惑がかかることをよく分かってますよ」
中野、阿部、吉川、高津と4人が語った紀行の印象には、共通項がいくつかある。勢いがある、意外と神経質。この「意外と」という修飾が、彼のキャラクターを端的に表しているように思う。一見すると神経質には見えず、豪胆なように振る舞っているけれど、でも、実際には繊細であるということだ。それはピットで僕が見た、足を投げ出してチェアに腰掛けながらもスタッフの動きに注意を払う紀行の姿とオーバーラップした。
そして、名古屋に住んでいるということ。レース以外での紀行の素顔を聞こうとすると、各人が名古屋という地名を口にし、彼はそこに帰っていくから分からない、と言った。
結局僕は、この日ほとんど紀行と話すことがなかった。彼の素顔に近づくには、もっと時間が必要そうだし、サーキットでは難しいのかもしれない。
僕は、彼の住む名古屋に行ってみることにした。
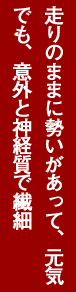
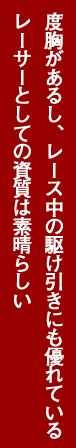
「今年、芳賀紀行がチャンピオン獲ったしさ、4ページで何か原稿書いてね」
これがWAY編集長、Iさんのリクエストであった。4ページのために、SUGOでのレース取材、それに彼の実家での取材機会を与えられた。本来は「チャンピオンを獲ったこの1年を振り返る」という原稿が期待されていたように思う。しかし1年前のノリックの時と同様、そこには収まりきらなかった。
取材を終えて書き始めてみると、驚くほど筆が進む。 SUGOでの取材分だけで、4ページ分のスペースはあっと言う間に終わってしまった。恐る恐るIさんにその旨を伝えると、「マジかよ、しょうがねえなあ」と言いつつ、比較的すぐに「分かったよ、次で終わらせろよ」と、4ページを追加してくれたのだった。本当は、さらにもう4ページ追加してもらって、前・中・後編という構成にしたいぐらいだったが、ありがたく4ページをいただき、全8ページとなった。
このWAYはヤマハ発動機発行のPR誌で、いわゆるクライアント仕事である。だからページの中身や構成をおいそれと変えることなど、本来まかりならぬこと……なのだが、Iさんが関係各位に頭を下げるなど、ずいぶんと骨を折ってくださった。
Iさんに迷惑をかけてしまうことは重々承知の上でも、筆が止まらないという感じ。それぐらい芳賀紀行は、僕にとっては魅力ある人物だったのだ。
紀行は決して口べたではないが、饒舌ともいいがたい。「インタビュー」とは言っても、彼との対話だけでは僕の主観や感想を中心に据えざるを得ない。それは避けたかった。「僕」は語り部であって、主役ではないのだ。そこで、とにかく彼の周辺にいる人たちから、芳賀紀行の人物像を浮き彫りにしたいと思った。