 '
'
'97シーズンを締めくくった全日本ロードレース最終戦では、
ヤマハ・ファクトリーの各々に芳賀紀行について語ってもらった。
そして紀行の人間像により深く迫るため、
実家・名古屋の銭湯で家族を交えてのインタビューを行った。
菅生での紀行が仲間たちの中にあったように、
名古屋での紀行は、家族の中にあった。
【後編】
■ヤマハ発動機発行「WAY」1998年1/2月号掲載・1997年11月取材
家族の中の紀行
約束の午前10時に、紀行の実家である白鳥温泉に車を着けた。そして、僕とカメラマンの高島は車中で顔を見合わせ、次の瞬間、慌てて車を飛び降りた。
紀行と健輔、そして父親の信夫が、路上で僕らの来訪を待っていたのだ。
11月の前半、寒さがそろそろ身に沁みてくる時期だ。しかも直前のTBCビッグロードレースで紀行は転倒し、右肩を傷めている。
それぞれと挨拶を交わし、銭湯ののれんをくぐろうとした時、紀行が、
「泊まりはどこだったんですか?」と尋ねてきた。僕がそれに答えると、何かを含んだようにニッと笑った。それは初めて見る表情だった。だが、その悪戯っ子のような表情は、この後しばらく彼の顔に浮かんでくることはなかった。
脱衣場の丸椅子に膝を抱えて座った紀行は、ときおり大あくびをしながら、つまらなそうな顔をしている。紀行に対する質問を、信夫や母親のかおる、それに健輔が引き継ぐこともしばしばだった。
思い返せば、この日の出会いには、紀行と家族のあり方が凝縮されていたようだった。
チャンピオンになった今シーズン、振り返ってみるとどんな1年でしたか?
「どんな1年だったか……? どんな1年。うーん。普通の1年」
普通で、チャンピオンってなれるもの?
「序盤戦ってみんな調子良くないけど、そっからの意気込みが違ってたから。あと環境も」
紀行の口数は少ない。
お兄ちゃんから見ると?
「環境や体制は確かに整ってたと思うし、僕なんかから見てるとうらやましい部分もあった。でも、紀行も人にできないことをやってるからね。それに確かに勢いはありましたよね」
芳賀兄弟とバイクとの付き合いは長い。ポケバイに乗り始めたのは、健輔が5歳、紀行が4歳の時だ。偶然、祖母が新聞記事で見つけた遊びだった。
信夫が言う。
「見に行って面白そうだと思ってね。健輔がやることは全部紀行もやるから、同時期に始めました。何でも一緒じゃないと紀行が嫌がるんでね」
兄弟に同じことをさせるっていうのは、芳賀家の方針ですか?
笑いながらかおるは否定する。
「いいえぇ。ただ紀行が何でも真似したがるってだけのこと。お互いライバル意識が強くてねぇ」
そうなの?
「自分では分かんない」
何でもお兄ちゃんの真似をする一つ年下の弟は、ぶっきらぼうにそう答える。
何でも真似される兄は、
「昔のことだからオレもよく覚えてない。でも、初めて名港の埠頭に乗りに行った時、真っ先に親父が乗って、転んで擦りむいてケガしたってことだけはよく覚えてる」
笑っている。
両親ともが、紀行は健輔の真似をするものだと思っている。しかし兄の健輔は、紀行を語るとき、真似された、とは言わない。
「変に気を使うヤツなんですよ。でも、僕もどうでもいい事に気を使うから、似てるとこあると思う。……考えてることとかやってることとか欲しい物とか、似てる」
似てる、と言うのだ。
お兄ちゃんとしての意識は?
「いっつも見られてるんだなぁと思いますね。でも、常に兄弟愛はあると思う」
この懐の深さは、間違いなく幼かったころの兄・健輔に対して、信夫とかおるの深慮があったことを窺わせる。
両親の間では、健輔の見方は一致している。自分のことはキッチリやる。お小遣いにしても、「金のない時は言えよ」と話しても、決して甘えてこない。
そしてふたりが異口同音に言う。
「そういう点でも、紀行の方が甘え上手だね」。
紀行が健輔の後を追わなかったのは、高校進学ぐらいかもしれない。
健輔は中学卒業後、高校に進学し、同時にレース活動も続けた。しかし2学期で退学する。やはり本格的なレース活動との両立は難しいし、3ナイ運動が盛んな土地だったということもある。愛知県は全国的に見ても学校教育に厳しい土地だ。
その時中学3年生だった紀行は、
「学校のことなんか考えてもみなかった」。
何のためらいも障害もなく、高校には進学しなかった。
「ミニバイクでいい成績出てたしね。進学どうのこうのなんて、僕らも気にしなかったですね」
この信夫の言葉には、「悔いのない人生を送ってもらいたい」という願いが込められている。信夫はかつてパイロットを目指し、単独飛行まで経験している。しかし、「いろんな事情があって」その道を断念した。
「紀行たちは、自分の好きなことをそのまま職業にしてる。うらやましいですよね。もしタイムスリップできたら、僕だって絶対にもう一度パイロットを目指すと思う。子供たちには悔いの残らない生き方をして、そして大きな人間になってほしい。ただし、人に迷惑をかけない範囲でね」
放任主義で育ててきたんですよ、信夫は苦笑いしながらそうも付け加えたが、ただ放任してきただけで、ある世界で頂点に立つような子供が育つとは考えにくい。しかも、兄弟ともが。
母方の祖父、光本庄一は、73歳になる。歩くのは少し難儀そうだが、かくしゃくとしていてとても元気だ。レースの詳しさ、見方の深さには、思わず感嘆する。
庄一は何度もサーキットに足を運んでいる。もちろん、両親も。
孫たちがレースしてるのって、見てて心配じゃないですか?
「心配ちゅうより、勝たないかな、とね」
「競輪や競馬を見に行くのと同じようなつもりでいるらしいんですよ、じーちゃんは。レース前に予想するんだよね」
健輔は「じーちゃん」にそう笑いかけて、すぐに真顔になる。
「サーキットにじーちゃんやばーちゃんが来るようになって、周りの人たちに『あ、こいつら意外におじいちゃんおばあちゃんを大事にするんだ』って思われるようになった。『今時の若者にしては』って、珍しがられて。でも、オレたちとしては別 に普通のことをしてるだけ。意識してることなんか何もないのに、周りに高く評価されてるなんて、そっちの方が意外でしたよ」
じーちゃんは、目を細めて煙草を吸っている。
昨年の6月、紀行は実家を出て、一人暮らしを始めた。実家からは車で10分ほどの離れたマンションの一室だ。部屋のそこかしこに、紀行のライディングの写 真を大きく引き伸ばしたパネルが飾られている。キャビネットにはいくつものヘルメットが収められている。
「集めてるんですよ。これは去年の8耐でオレがかぶったやつ、これは難波さんの、これはお兄の……」
紀行は、健輔を「おにい」と呼ぶ。
カウンターキッチンのそばに置かれたテーブルには、クロス代わりにヤマハレーシングチームの白い旗が敷かれている。
キッチンには一通りの食器類が揃っているようだが、コーヒーを入れてくれようとする紀行と母の間から、
「フォークとか何にもないよ」
「買って来なくちゃね」
のんびりした会話が聞こえてくる。
21歳の青年が一人暮らしをしている割には、部屋はきれいだ。というより、あまり使われていないのだろう、LDK以外はほとんど空き部屋で、殺風景だ。
「ここにはほとんど寝に帰ってくるだけなんで」 と言う紀行の言葉のままだ。
レースやテストで紀行が長く家を空けるときは、信夫とかおるが泊まり込みで留守番をすることもある。ここ、私たちの別 荘なんです、とかおるが笑う。
実家を出たのは、手狭になったから。
「親としても、子離れができたかなって」
と、かおるは言う。
紀行が自分で食事を作ることはほとんどない。たいてい外食だ。洗濯は自分でするが、
「めんどくさくなったら実家に持ってっちゃう」。
紀行に話を聞いている間、かおるはこまごまと部屋を掃除していた。
「銭湯なんかやってると、なかなか来られないですからね。紀行がいない時は、お父さんと掃除していくんですよ。……掃除してくれる人でも見付かればねぇ」
紀行は呑気にソファに寝そべっている。何しろ、実家からは車で10分足らずしか離れていないのだ。
'98年、紀行は世界で戦う。高速サーキットが多くなるのが心配だ、と信夫は言うが、でも、と続けた。
「でも、こればっかりは何とも言えないね……。ゆっくり走れとも言えないし。まあ、小さいときからバイクに乗ってるから、転んだときの対処の仕方とかを体で覚えてると思うんですよね。ケガしても大丈夫だろうと思うしかない」
「心配するぐらいだったら、やめさせてますよ」
かおるはきっぱりとしているが、しかし紀行に向ける眼差しはいかにも母親らしいものだ。
「コワモテだけど、優しい子なんですよ。若い頃って、ほら、肩で風切って歩きたい時期があるじゃないですか。22、3なんてね、親からしてみればまだガキなんですよ。8耐で勝とうが、全日本チャンプだろうが、ガキ」
もし世界チャンピオンになったら……?
「世界チャンプになろうが自分の子ですからね、ずっとそばで見ています」
そう言いながらも、かおるは紀行が人間的に大きく成長してきていることを認めている。
「ずいぶん大人になってきてはいるなと思ってます。レースの世界に入って、たくさん社会勉強を積んだんでしょうね。学校では習えないことを学んでくれてると思う」
信夫もうなずく。
「そういうことこそ、喜ぶべきことなんですよ、チャンピオン云々を言う前にね。シーズンが終わって日本に帰ってきたとき、どういう大人になってるか、それが楽しみですね」
紀行の自宅のルーフバルコニーからは、名古屋駅とテレビ塔、それに名古屋球場も望める。
「夏は港で打ち上げられる花火も見えるんですよ」
カメラマンが部屋に戻り、バルコニーには僕と紀行だけが残った。強い風に吹かれながら、僕と紀行は、ちょっとここには書けないようなプライベートな話をした。その時彼は、この日最初に見せた悪戯っ子の顔になった。
(文中敬称略)
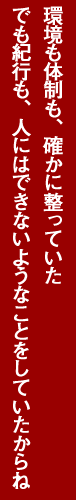
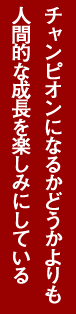
この原稿は、掲載時のものから少しだけ手を加えている。具体的には2つの段落を削除した。書きたいこと、言いたいことが多すぎて、未整理な部分があったからだ。逆に言えば、それぐらい、いろいろと考えさせられた。
2号8ページにわたって、紀行の人物像のある一面に触れることはできたと思う。しかしその後、1999年にイタリアで紀行を見た時、僕が書いた紀行の一面が、本当に些細な一面だったことに気付いた。
イタリア・モンツァサーキットに行き、WSBKライダーとしての紀行を見た。日本では考えられないような熱狂的なファンが多数押し掛け、紀行を取り囲むシーンを何度も見た。彼はイタリアのチームに在籍しているが、イタリア語はあまり話せない。英語も苦手だ。しかも無愛想。日本人である僕から見れば横柄にさえ見えることがある本場・ヨーロッパのモーターサイクルレースファンが、紀行の前ではおどおどしていた。
だが、人気は爆発的だった。その熱狂は、ストレートに彼のライディングそのものに起因しているとしか考えられない。走ることだけで、彼は人の心をつかんでいるのだ。もともとそういうタイプだった彼が、そういうファンがいるような環境でレースができることは、紀行にとってもファンにとっても、幸福なことだろう。
紀行のホームページの仕事をさせてもらっていて、ファンから寄せられるメッセージを目にする機会があるけれど、その多くは男性からで、ライディングに魅力を感じている人が多い。中野真矢宛のメッセージの多くが女性からであるのとは対照的で、男臭い、「応援団!」とでも言いたくなるような雰囲気だ。
紀行の、そのように男を惹きつける魅力を伝えられる原稿を書けないだろうか、という望みが、ずっとあった。それは2000年の8耐で、少しだけかなえることができたように思う。