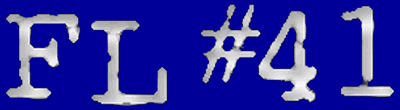
モニターに、ゼッケン41番を付けたYZF-R7が大きく映し出された。
179周目、2分8秒785のファステストラップをマークした芳賀紀行の走りだ。
トップからは10周以上遅れていたが、 その瞬間の主役は、間違いなく彼だった。
タイミングモニターに表示された、 ファステストラップを示すアルファベットFLと車番41は、
いかなる障害にも屈しない彼の魂のように、
レースが終わるまでついに消えることはなかった。
■ヤマハ発動機発行「WAY」2000年9月号掲載・2000年7月取材
ヤマハWSBKチームのケータリングは、とてもおいしいイタリアンを出すと評判だ。プレス関係者もよく顔を出し、パスタなどをぱくつく姿が見られた。もちろん、チームのエースライダーである芳賀紀行も、ここで食事をとる。
彼が食事を始めて間もなく、メカニックのロビン・ブリビオがブーイングをした。それはそうかもしれない。評判のイタリアンに、紀行は日本から持ち込んだマヨネーズをブリブリとかけて食べていたのだから。
「信じられない……」
変な生き物を眺めるような視線のロビンに、「悔しかったら和食を食ってみろって。アイツ、日本に来ても一口も和食を食べないんだぜ」。
99年5月、ワールドスーパーバイク選手権のレギュラーライダーとして2度目のシーズンを過ごしていた芳賀紀行をイタリア・モンツァサーキットに訪ねて、最も印象的なシーンだった。
自分のスタイルは変えない。周りに流されない。どこにいても、自分は自分──。
糊の効いた真っ白なテーブルクロスの上に並べられたイタリア料理。その横にデンと置いてある赤いキャップのマヨネーズ。それは、芳賀紀行の生き方そのものだった。
7月21日、金曜日。鈴鹿8時間耐久ロードレースの計時予選は、ウェットになったりドライになったりと目まぐるしくコースコンディションが変わり、出走タイミングによってタイムが左右された。ゼッケン41番、ヤマハレーシングチームの吉川和多留/芳賀紀行組は、吉川が7位 、紀行が4位。二人のライディングの違いから、車体セッティングに迷いがあった。
土曜日は、1台ずつ走行して決勝グリッドを決めるスペシャルステージが行われる。ここは自分にとっての大きな仕事の一つだ、と紀行は思っていた。
前日のナイトセッションで転倒し、多少体を傷めてはいたが、それは紀行にとって問題ではない。問題は、自分のやるべきことをやれるかどうか、その一点だった。紀行は、このセッションに限っては自分の走りやすいセッティングを要求した。
第1ライダー、吉川和多留のタイムは2分8秒968。
「僕の仕事は、無理しないでそこそこのタイムを出して、ある程度の順位を押さえておくことですからね。そういう意味では満足です。あとは紀行が決めてくれるでしょう」
吉川としては必ずしも口に出したい言葉ではないだろう。7歳年下の紀行を弟のように可愛がってはいても、まったく同じマシンに乗る最も近いライバルなのだ。
ジャンプアップステージの12番目に出走した紀行は、2分7秒836。ここまでで最も速いタイムだ。しかし、残り8台。各ファクトリーチームが出番を待っている。アレッサンドロ・バロス、加藤大治郎、バレンティーノ・ロッシ……。誰も紀行のタイムに届かなかった。
最終走者は、カワサキの井筒仁康。計時予選ではただ一人2分7秒台をマークし、他を引き離していた。勢いがある。中間タイムで、井筒はわずかに紀行を上回った。控え室のモニターで、紀行はその走りをじっと見つめている。そして緑のマシンがチェッカーを受ける。2分7秒838。1000分の2秒、紀行のタイムが抑えきった。ポールポジションが確定した瞬間、紀行は部屋を飛び出し、ピットに駆け込んだ。スタッフが、大きな拍手と歓声で紀行を迎える。
「ホント、やってくれますよ!」
チーフメカニックの星野仁がそう言ってニコッと笑った。それはチームスタッフ全員の思いだった。
日曜日、決勝レースのスターティングライダーは吉川和多留。紀行は、「スタート前さ、あそこで待ってると暑いじゃん。マシンまで走るのも疲れるし……」。そしてちょっと小さな声で「それに、緊張するかもしんないし」と付け加えた。
スタートして8周目までは、ゼッケン41番のYZF-R7を含む5台がトップ集団を形成していた。しかし9周目あたりから早くも周回遅れが出始めた。周回遅れをかわすタイミングの違いで、集団は微妙にちぎれ、また接近する。
いいタイミングで周回遅れを処理できず、トップからやや遅れをとって、吉川は焦っていた。レースは始まったばかりで、ゴールは7時間以上も先だ。しかし、井筒仁康や玉田誠など、勢いのあるライダーたちに何とか着いて行かなくては、という思いが、吉川のアクセルワークを微妙に狂わせていた。
16周目、周回遅れが途切れ、前が空いた。ベテランの吉川が、自分を抑えきれずにアクセルを開けていく。10周目あたりから、リアタイヤが予想より早くグリップを失ってきていた。そのことは分かっていた。だが……。
130Rでリヤからスライドダウンし、転倒した。YZF-R7はフロント周りが大破。吉川は無事で、マシンを押してピットまで戻ったが、マシンを修復して紀行がピットを離れた時には先頭からすでに数周遅れていた。
「取り返しのつかないことをやっちゃいました」
吉川は言った。確かにこの時点で、ゼッケン41番の優勝は事実上消えた。
あるチーム関係者は、「こうなると正直なところ、帰りたいぐらいですよ」 と渋い表情を見せた。
しかし芳賀紀行は、まだ自分の「仕事」を終えていない、と思っていた。
吉川の転倒を見て、紀行は「やられたぁ!」と思った。しかし、腹を立てたり責める気持ちはまったくなかった。車体のセッティングが詰め切れていなかった面もあったし、レースをしている以上仕方がないことだ。
「オレだって100%確実に走れる保証なんてないしね。誰しも転ぶ可能性はあるんだからさ。それより、すごくいいポジションで走ってくれてたからね」
ピットアウトした紀行は、1周してすぐにピットに戻った。外装パーツを交換し、応急処置を施して走り出してはみたものの、マシンは想像以上にダメージを受けていたのだ。ステムもフレームも曲がっていて、まともに走らない状態だった。
マシンを再修復してコースに復帰した時、ゼッケン41番はトップから10周以上遅れていた。紀行は、傷んだマシンを走らせながら、自分のやるべきことは何かを考えていた。目標だった優勝の望みは絶たれた。だが、オレにしかできないことがあるはずだ……。
そして彼が出した答えは、テレビに映ることだった。
「いい走りをすれば、実況のミシナさんがカメラをスイッチしてくれるはずだ」
そう思った。
1回目のセッションでは、走行し始めてすぐ、2分8秒820をマーク。タイミングモニター上では、しばらくこのタイムがファステストラップとして記録されていた。しかし、走りは映らない。 「セッションを終えて戻るたびに、トレーナーの先生に『映っとった?』って聞いたんだけど、『映ってない』って言う。どうしたら映るかなーって考えたんだけど、結局いいラップで走るしかできないじゃん、ライダーなんて」
3回目までのセッションでは、暑さからタイムが出せないだろうと踏んでいた。気温が下がった最後のセッション、紀行はスペシャルステージで履いたタイヤを選んだ。路面温度が高い時は車体とのマッチングがうまくいかなかったが、今なら大丈夫だろう、と勝負に出たのである。
この時点でのファステストラップは、83周目に2分9秒653を記録したゼッケン4番、キャビンホンダレーシングチームのものだった。
タイヤチョイスは成功した。クリアラップを得た紀行は、完璧な状態からはほど遠いマシンで、2分8秒785というファステストラップを叩き出したのである。8時間の決勝を通じて唯一の8秒台だった。
思惑通りカメラは紀行にスイッチされ、そのライディングを追った。
「あー、映ってる映ってる」
2コーナーに設置されたサーキットビジョンで自分が映っていることを確認しながら、紀行はマシンを走らせていた。
午後7時30分、チェッカーフラッグ。トップからは14周遅れの18位だが、紀行はマシンを高々とウイリーさせてチェッカーを受けた。
「お客さんにさ、『芳賀紀行、どこにいたの?』って思われるの、シャクじゃんね。おいしいとこ見せとかないとさ」
こうして芳賀紀行にとって8度目の8耐は終わった。
ファステストラップもウイリーも、ただ彼自身が目立ちたかったからではない。レース後の紀行は、自分でグローブを外せないほど両手を傷めていた。満身創痍のマシンをファステストラップの座に押し上げたのは、他の何物でもなく、彼の体なのだ。レースを終え、チームスウィートルームに戻った紀行がドリンクに手を伸ばす。コップを持つ手はブルブルと震え、中のドリンクが小刻みに波打っていた。
それでも、「監督を立てないと、と思って頑張りました」と少しおどけた口調で言う。
そばにいた鈴木孝明監督は、「いやもう、紀行くんには参りましたよ」と、苦笑いするばかりだった。後で紀行のいない場所で鈴木監督は、「彼には本当にありがとうと言いたいですね」と言った。
ヤマハファクトリーにとっては、ゼッケン41番の転倒の後、ゼッケン8番の辻村猛/サイモン・クラファー組もチェーン外れのトラブルに遭い、散々な8耐になってしまっていた。そんな中で、紀行がマークしたファステストラップだけが、ヤマハにとって、YZF-R7にとっての光明だったのだ。
「ヤマハの看板を背負ってるエースチームだからね。何とかチームを立てないと、と思ってた。たくさんのスタッフが2人のライダーのために一生懸命やってくれてるんだもん。優勝できなくても、オレはオレのできることを精一杯やんなくちゃ」
マシンが壊れていようが、走りにくかろうが、そんなことは関係ない。紀行はいつも通り、自分のやるべきことをキッチリとやったのだ。
「だから悔いはない。楽しかったよ」
ビールかけで解放感に浸るプライベートチームを横目に、ヤマハレーシングチームはそそくさとピットを片付けると、電灯を消してテントを閉じた。2000年8耐の18位という順位は、勝利を義務づけられた彼らに何も残さない。
しかし179周目に紀行が見せたラップは、こんな風に鮮烈な記憶として残るだろう。
「あの年って、紀行がすげえ走りでファステストラップを出したんだよな。……順位は思い出せないけどさ」
8耐を終えた紀行は水曜日に日本を発ち、イギリスに向かった。彼の「仕事」は終わらない。
8耐直前になって、「カッチョイイ芳賀紀行を書いてね」と、WAY編集長のIさんにオーダーされた。ついに「シーズン振り返りインタビュー記事」や、「対談形式ね」ではなく、「カッコいい原稿を書け」というリクエストが来たのだ。
今までは、出来上がった原稿を恐る恐るお見せしていた。なぜなら、当初の編集企画とはどれもまったくもって食い違っていたからだ。
「こんな風になってしまったんですけれども、もし良かったらコレで何とかお許しいただけないでしょうか」
ドギマギしながら原稿を渡していた。でも、今回ばかりは違う。堂々と書きたいように書けばいいのだ。
その反面、難しいだろう、とも思っていた。確かに僕は芳賀紀行という男を非常にカッコいいとは思っている。だが、8耐でカッコ良さを見せてくれるかどうかは分からない。しかも8耐には主にはインターネット広報業務のために行くので、僕自身とても忙しく、じっくりレースを見る余裕がない。楽しみだけれど、心は重かった。
レースが始まって、序盤で吉川和多留が転倒した時は、これで終わりだと思った。カッコいいも何も、あったものじゃない。修復して再スタートは切ったけれど、ピットで修復される#41のマシンを見ると、とてもではないがまともに走れるような状態ではなかった。
でも、やってくれた。見事なファステストラップだった。
原稿を渡し、「WAY」の色校を見て驚いた。3ページだったはずの今回の企画が、4ページになっていたのだ。「書きすぎなんだよ、オメーは……」とIさんに言われた。また約束を破ってしまった……。