
■ヤマハ発動機発行「WAY」1997年2月号掲載・1996年12月取材
きれいに晴れわたった冬の朝、僕は渋谷から東急東横線に乗り、自由が丘に向かった。乗客は全員がシートに腰掛けていて、まだ空席がある。男性客はほとんど全員がスーツにラクダ色、濃紺、濃緑のコートを羽織っている。女性客は中年が目立ち、誰も化粧が濃い。渋谷と横浜を結ぶこの路線は、いつ乗っても女性の浮わついた気分を感じる。車内はたまに押し殺したような女の笑い声が聞こえるぐらいで、とても静かだ。向い側の座席に座る聾唖の高校生カップルが、口元に笑みを浮かべながら激しい手話を楽しんでいる。僕にその内容は分からない。録音された車内放送の女性の声が、ふわふわと漂う。電車は暖かな日差しを浴びながら走る。
自由が丘の駅は、階段だらけだ。東横線と大井町線が十字型に交差するこの駅は、やたらと階段が多い。階段を降り通路に出ると、四方に上りの階段があり、右奥には大井町線のホームが見える。開放感があるような、閉塞されているような、奇妙な空間だ。
駅前には、13の通りがある。すずかけ通り、わかくさ通り、しらかば通り、ひのき通り、からたち通り、つばき通り、ガーベラ通り、カトレア通り、マリ・クレール通り、グリーンストリート、メイプルストリート、ヒルサイドストリート、サンセットアレイ。真冬日の午前中に、これらストリートを大手を振って闊歩しているのは、紙袋を提げた中年女性だ。彼女たちの頭はたいていおばさんパーマで固められているが、決してストリートの雰囲気とは遊離していない。個々の洒落たショップの前では、確実におばさんパーマは異質だ。しかし自由が丘という街には、リアルにマッチしている。
駅正面出口を出てすぐ右手には、4階建ての自由が丘デパートがある。中央の通路を挟んで左右に雑多な店が展開する、古い造りの百貨店だ。中には洋品店、靴屋、パブ、スナック、呉服屋、ダンス用品店、金物屋、鮮魚店、瀬戸物屋などがひしめきあう。通路を歩くと、おばさんパーマが前方にずっと列になっている光景が見える。自由が丘の駅名はかつて九品仏だったが、昭和4年に大井町線に同名の駅ができたことから改名した。自由が丘という名称は、地元にある自由が丘学園という校名からつけられている。
そんな街で、阿部典史は育った。昭和50年に生まれた阿部は、自由が丘周辺で何度か移転しているが、離れたことはない。去年2月に完成した新居も、自由が丘駅の徒歩圏だ。
玄関を入ると、すぐに階段があり、2階に通された。明るい色のフローリングに白い壁紙。白熱灯の照明が暖かみのある光を放つ、清潔な家だ。2階の応接間には本革のシックなソファがあり、阿部はそこに座るように勧めてくれた。正面にはテレビセットが置かれている。右側の壁にはトロフィが4つとシャンパン、表彰台の写真、そして阿部のライディングのポップアート。ひときわ大きいトロフィにはMarlboro Grand Prix of Japan 500cc CLASS WINNERとある。大振りなSegura Viudasのシャンパンは封が引きちぎられていて、生々しい。
阿部は幅のあるソファの僕のすぐ左隣に、長い足を大きく開いて座った。阿部は去年の11月、年を締めくくるTBCビッグロードレースで転倒、鎖骨を骨折し、まだ完治していなかった。そのため、事前にアポイントメントを取った時には、寒いと傷が痛むので外での撮影はなるべく短くしてほしい、と言われていた。
まだ、痛む?
「普通に生活してる分には大丈夫だけど、物を持ち上げらんない。ゲーセンのクルマのゲームもできない。でも、軽いトレーニングは始めてます。今日もこの取材が終わったらジムに行くんですよ」
足もとに真っ白いふわふわした猫がいる。阿部は時折足で猫の横腹をあっち行けよというように軽く押しやる。猫は阿部の足にまとわりついて離れない。トレードマークの長い髪を時折掻き上げる。細い目は、決して泳がず真っ直ぐに僕の目を見ている。白目がきれいに澄んでいて迷いがない。
「レーサーって、全員そうだと思うけど、自分だけは絶対コケないって思って走ってる。今まで数え切れないほど転んでるんだけど、でも、自分だけは転ばないと思ってるし、転んでもケガしないと思ってる」
コケて、骨折してても?
「そう。ケガしても、あぁ、あん時はコケ方が悪かったなとか、ツイてなかったんだなとか」
死ぬなんて?
「全然思わない。……でも、そう思いこもうとしてるってとこもあるかな」
ソファの横には、美容室でパーマをかける時に頭からかぶる、ドライヤーのようなものがあった。センスの良いシンプルな室内にあって、ドライヤーは異様なたたずまいだ。黒と白のダンダラ模様のプラグコードが柄の部分に巻き付いている。阿部のお母さんはパーマをかけていないが……。
お母さん、これでパーマを?
まさか、と笑いながらお母さんが答える。
「まさか。これ、骨折の治療用の器具なんですよ。遠赤外線だか、太陽光線に近いものが出るらしくて。買ったんです」
ケガは心配じゃないですか?
「それは、とても心配です。いつもレースが終わって2時間ぐらいの間に電話をくれることになってるんです。たまに電話がなかなか鳴らないと、あぁ、何かあったのかなって。連絡が遅れて、いい風には考えないですからね」
サーキットには?
「ほとんど行きません。息子が来るなって言うんです。恥ずかしいみたいで」
誰もが味わう授業参観日のあの気分。恥ずかしい、でも来て欲しい、でもやっぱり来るな。結局親には「来るなよ。来なくていいからな」と念を押し、教室でその姿を発見すると逃げ出したくなる。でも……。
どうしてお母さんが来るとイヤなの? いいじゃない。
「だって、めんどくさいですよ。レース以外のことに何だかんだって気を取られちゃいますから」
家での簡単なインタビューを終え、外での撮影に移ろうという時にお母さんが、コーヒーいれましたから飲んで下さい、と言った。阿部は「何で話してる時に出さないんだよ。これから外行くのに」「だって話途切れちゃうかなと思って」「話しながらだってコーヒーぐらい飲めるじゃんか」
結局もう一度腰を降ろし、コーヒーを飲んだ。
出かける間際、僕は阿部に部屋を見せてもらえないだろうか、と頼んだ。え、ちょっと待ってくださいよキレイにしますから。超汚いんですよ。いやいや、写 真は撮りませんから。書くけど。阿部は苦笑いを浮かべながら部屋を見せてくれた。
玄関に入って右手奥にある6畳ほどの洋間が、阿部の部屋だった。白熱灯の明かりが、柔らかな黄色で部屋を満たしている。ベッドにはモノクロの柄が入った掛け布団がふわふわしていて、頭のあたりにはスノーボードが立てかけてある。黒づくしのオーディオ。銀色のマウンテンバイクには、無造作に洋服がかけられている。窓際、壁と天井の突き当たる角に、赤い紙でできた四垂のようなものが貼り付けてある。
あれは?
「何だろう。よく分かんない。お母さん、あれって何?」
「何て言うんでしょうね。たぶんお守り……。私にもよく分かんないけど……、家の南側に貼るといいらしいんですよね。何て言うんだろう、あれ」
外に出ると、阿部は「あぁ、今日はあったかいですね」とのんびり言う。その日、東京地方の最高気温は17.4度で、例年を5度以上も上回っていた。阿部はゆっくり歩く。僕は阿部にあれこれと話しかけながら、横に並んで歩く。家から出てほんのわずかな距離に、乱雑に資材が散らかった工務店があって、道路沿いには鳥類が押し込められた10数個のカゴがずらりと並んでいる。湿っぽく、日光の当たらない暗いカゴだ。中では鶏、鴨、十姉妹、セキセイインコが小さな生活を営んでいる。
「うわ、こんなとこに鳥がいたんだ。全然知らなかった」
家のすぐそばじゃない。
「だって、たいていクルマですから。この辺歩くのすっげー久しぶりなんですよ。えー、知らなかったな。何だろう、これ」
阿部は何度か振り返る。阿部の家からその工務店まで、50メートルもないだろう。しかし阿部の住む世界は、「この辺」ではないのだ。
動物、好き?
「大好き。うちに猫いたでしょ。あれ、オレが9年前に拾ってきたんです。2時間かけて友達と羽田までチャリンコで行ったことがあるんですけど、その時に捨てられてるのを見つけて」
ああ、白くてふわふわしてた……。かわいかったな。
「もう一匹、灰色のもいるんですけど、2匹を片手に抱えて連れて帰った」
反対された?
「されたされた。夏休みに拾ったんだけど、夏休み中に捨ててこいってお母さんに言われた。その頃は賃貸マンションだったから。でも、お母さん情が移っちゃって、結局飼うことになった。お母さんは白い方をクンクン、グレーの方をタンタンって名前つけてるけど、そんな風に呼ぶのはお母さんだけ。オレと兄貴は単純。白と黒って呼ぶ」
阿部の兄はプロゴルファーをめざして修行中だ。今は渡米している。
阿部は僕と距離を取らずに、僕の真横にいる。時折ふわりとこちらに近づき、肩と肩が触れそうになる。こういう無防備な距離感は、きっと育ちの良さから来ている。
家は、裕福だった?
「自分ではあんまり思わないけど、周りの友達とかと比べると裕福だったかもしれない」
今は?
「中学時代の友達と遊ぶこともあるけど、今あいつら学生だからなー。それに比べればね。欲しいと思ったものはほとんどすぐ買えるし、やっぱ財布の中身も違う」
じゃあ、うらやましいだろって感じ?
「そんなことない。あいつら見てると、悩みがないっていうか、遊んでられていいなって思う。オレだって遊ぶけど、ずっとレースのこと引きずってる。下手なことできないってどこかで抑える気持ちがあるから」
いいだろうって思うことは?
「好きなことがそのまま仕事になったってことかな。なかなかそういうヤツいないもん」
阿部は中学3年生の時に、レースの世界に入ることを決めていた。卒業した阿部はアメリカに渡り、レースを学んだ。同級生で、同じように高校に進まなかった者も4、5人いる。受験だ受験だと周りが目の色変えている時、「高校行かない組」で遊び回っていたことは、阿部のとても楽しかった思い出のひとつだ。
「でも、オレははっきりやりたいことがあって、自分でこの道に進むって決めてたから、他のヤツらとは違うと思ってたけど」
今やグランプリのトップライダーだもんね。その時の連中、驚くよね。
「家が自営業で、継ぐってヤツらだったかな。ひとりは今も付き合いがある」
ずっと住んでいる土地だけあって、地元に阿部の友人は多い。一緒に吉野家で牛丼を食べたり、ラーメンをすすったりもする。取材中、自由が丘駅前で男女ふたり連れの友人に出会う。おー、と叫びあい、「チョー偶然じゃん」と阿部が言う。女の子が「こないだの写 真できたから」と笑う。ほんの少し言葉を交わし、別れた。男友達を指して、阿部が言う。
「アイツと一緒にスタンドでバイトしたことあるんですよ。16歳で、まだノービスだったかな。6カ月ぐらいだったかな」
楽しかった?
「自分で働いてお金をもらえるって、何かうれしかったな」
今も?
「今は、好きなことやってお金までもらえちゃっていいのかなって感じ」
撮影中に、おばさんがカメラと阿部の前を遮る形で横切った。阿部は「どうぞ」と手を広げる。駅に向かって歩いていると、オカモチをがしゃがしゃいわせながらビジネスバイクが追い抜く。バイクは阿部に気づくと停車して、おー、どう? 今度はチャンピオン取れそう? と話しかける。んー、分かんないよー、髪を掻き上げ笑いながら阿部が答える。ビジネスバイクは、がんばってよ、という声とがしゃがしゃいう音を残して走り去る。レストランで食事をする。阿部はひとつしかないメニューを僕とカメラマンにも見えるように置く。食事が終わり、会計を済ませると「ごちそうさまでした」と頭を下げる。
なぜこういう阿部を見ていちいち不思議に思うのだろう。21歳でロンゲ、ダボダボのパンツを履いたイマドキの青年なのに、好感が持てて礼儀正しいから? それもあるだろう。でもそれだけではない。彼がグランプリライダーで、頂点にも立ったことのある男だからだ。つまり僕は、そういう男はどこか普通 じゃないと思いたいのだ。どこか普通ではない部分を探り当てて、安心したい。やっぱりアイツらまともじゃないんだ、だからあんなバケモノみたいなマシン操ってレースして、勝てるんだ、と。
でも、目の前の阿部はあくまでもキチッとしている。もちろん僕は取材者で、阿部は被取材者で、お互い仕事として会い、会話をし、食事して、歩いている。阿部は、そういう意味で完璧に「阿部典史」を演じていて、まったく破綻がない。聞かれたことに答える。聞かれないことは話さない。
変な質問だけど、自分で、自分が異常だと思えることって何かない? ああいうマシン操れるってことは、どこかおかしいんじゃないかと思うんだけど。
「うーん、オレすっげー負けず嫌いなんですよ。じゃんけんとかゲームとかくだらない遊びでも、絶対に負けたくない。レースにハマッたのだって、兄貴がもともとモトクロスやってて、負けたくなかったからだもん」
才能は、あると思う?
阿部は困ったような笑顔を浮かべて、僕の目を見ながら首を傾げた。この日初めて見せた複雑な表情だ。
「んー……。分かんないなぁ。自分では才能あるとはまだ思えない」
チャンピオンとったら才能あると思えるかな?
「……分かんないなぁ、どうだろう」
これはきっと世界を舞台に戦う者の、率直な感想だ。阿部はあるインタビューで、一昨年から始めたスノーボードについて「才能あると思う」と答えている。阿部が言うのなら、おそらくその通 りだろう。スノボも本格的に始めれば、きっと瞬く間に頂点に上りつめる。そして、今まで見えなかったさらなる高みが目前にそびえていることに気づくのだ。その時、スノボの才能があるか、と問えば、阿部はたぶん困ったような笑顔を浮かべて首を傾げるのだろう。分かんないという答えは、今阿部がレースの世界でトップの位 置にいることを際だたせる。
1勝して、次の目標は?
「また勝つこと」
チャンピオンとは言わないんだ。
「そんな、バカみたいじゃないですか、たった1勝したからって次の目標がチャンピオンなんて言ったら」
堅実なんだ。
「って言うか、自分やマシンの状況を判断したら、今どの辺まで行けるかとかって分かるじゃないですか。それ以上のこと言っても意味ないと思うんですよね。もちろんチャンピオンはとりたいけど、もっと勝ちたい」
日本GPでピットに戻り、ヘルメットを被ったまま「やったー」と両手を突き上げた阿部の激情、そしてこの冷静。阿部はレース後、特にうまくいかなかったレースの後には、全員のラップチャートを持ち帰り、どのセクションで自分は速いか、遅いかを、ライバルと比較しながら研究する。
終わったらサクサクしてるのかと思った。
「伊藤(真一)さんとか岡田(忠之)さんとかは、すごいサバサバしてるんですよ。でもオレはそうじゃなくて、予選とか調子悪いとすげー態度悪くなっちゃうんですよ、その日。でも、伊藤さんとか岡田さんとかと飯食いに行くと、全然普通 なの。だからオレ、怒られんの。おまえそんな悔しがってんじゃねえよって。明日があるだろって」
たぶん、阿部はレースの世界でだけ生きてきた。今の阿部の人生には、レースしかないのだ。
結婚とかって考える?
「えー、まだ全然考えない」
パパになった自分ってイメージできる?
「ぜんっぜんできない。それにオレ、子ども苦手なんですよ。どう接したらいいのか分かんない。どうやって話したらいいのか考えちゃう。あれかなぁ、いっつも大人の中にいたからかもしれない。すげー困っちゃうんですよ」
つまり阿部は、子供用の顔をどう作ったらいいのかが分からないと言っている。レースの顔、オフの顔、取材用の顔、息子の顔、弟の顔、友達用の顔。いくつもの顔を巧みに使い分けて阿部は生きようとしている。今日の阿部は、言うまでもなく取材用の「阿部典史」だ。でも、こんなことは、誰にだって当てはまる。誰だっていろんな顔を使い分けて生きている。
最後のカットの撮影に入ったとき、午後3時をわずかに回っていた。僕は阿部と4時間を過ごした。阿部の表情には少し疲れが見える。硬質なシャッター音が何度か響き、カメラマンが「はい、オッケーです」と言った瞬間に、阿部の表情は柔らかく崩れ、今までとはまるで違う笑顔になった。挨拶を済ませ、阿部と別 れる。阿部は一度も振り返らずに、自由が丘の雑踏に消えていく。バックにはパチンコ屋のどきついネオンが瞬き、スーパーのビニール袋を提げた暗い目をしたおばさんが阿部とすれ違う。
ひとりで歩いている今、阿部はどんな顔をしているのだろう。僕には軽く揺れる長い髪しか見えない。
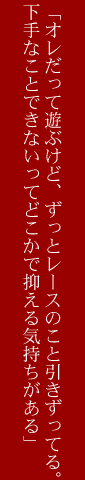
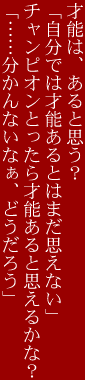
「ノリックにインタビューでもすっか?」
「WAY」誌の編集会議でそんな話になった時、ビックリして椅子から落ちそうになった。1996年、ノリックこと阿部典史は、ヤマハYZR500を駆って鈴鹿・日本GPで勝利していた。そんな世界のトップライダーに取材するというのに、編集長のIさんの口調があまりにも軽いことに驚いたし、まして僕がインタビューするなんて、夢にも思っていなかったからだ。
はっきり言って相当及び腰だった。取材前は、本当にイヤな気持ちがしていた。「あの」ノリックに会って会話をする……? どうすればいいんだ? 当時の僕は、二輪レース取材目的では、サーキットに行ったことさえなかった。ノリックが勝ったレースは普通の視聴者として、テレビで観戦していた。取材日は1996年12月17日に設定されていたが、できれば永遠にその日が来なければいいとさえ思った。僕にとって彼は、それほど「スゴイ人」だったのだ。
しかし残酷なことにその日はやってきて、僕はノリックとの時間を過ごし、会社に戻った。パソコンに向かっても、何も書けなかった。書いては消し、書いては消しを繰り返した。
編集会議では、「今シーズンを振り返るインタビュー記事」と決まっていた。
── 今シーズンを終えて、いかがでしたか?
阿部 そうですね、いろいろな経験が積めたシーズンでした。
というような記事だ。最初はその方向で書き始めたけれど、すぐに行き詰まった。僕がノリックと会って、感じてきたものはあまりにも多くて、こういう記事形態には収まりきらないことに気付いた。かなり早い段階で、僕は「インタビュー記事」の方向を捨てた。編集長のIさんは、カレンダーとにらめっこしながらも、僕がうんうん苦しんでいるのを静かに見守ってくださっていたし、勝手な方向転換も許してくれた。
かといって、どう書けばいいのかさっぱり分からなかった。「スゴイ人だ」と思っているものだから、放っておくと、どうしても無理にドラマチックに仕立て上げ、カッコつけて書こうとしてしまう。しかも、「ノリックに会った自分」に焦点を当ててしまいそうになる。ものを書いて生きていきたい、と漠然と思い、書く仕事をしていたけれど、方向性や方法論は何も身に付けていなかった。どうすればいいか分からなかった。
そんな時に、たまたま富士山麓で別の取材があって、ノリックの撮影をしたヒデヨシさんと同行した。ヒデヨシさんにはワガママを言える。取材後、無理を言って本栖湖に寄ってもらった。行き詰まって頭の中が爆発しそうになっていた僕にとっては、一つの契機だった。
どんよりとした冬の本栖湖は人気が全くなく、しんと静まり返っていた。本栖湖は山に囲まれているが、斜面がすとんと唐突に湖に落ち込んでいる。その斜面を、雲がゆっくりと流れ落ちていく。まるで滝のようだった。音はしない。けれど、ひどくダイナミックな滝だ。素晴らしい光景だった。
その光景を眺めながら、これをどう書けばいいのかな、と考えていた。どう書けば、どう書けば……。
そして、ふっと思った。
見たままに書けばいいんじゃん──。
見た以上に書いて、無理に盛り上げる必要はない。ストーリーを作り込む必要もない。僕が見たものは、すでに僕のフィルターを通しているのだから、「ノリックに会った自分」を書く必要もない。ただ見たものだけを紡いでいけば、それで十分なのではないか。そう思ったのだ。
再びパソコンに向かうと、今度はすらすらと書き進められた。不安がないわけではない。これでいいのかどうかなんて分からないけれど、今、自分に書けるのはこれだけだ、と信じるしかなかった。
原稿ファイルの最終修正日は、12月25日。取材を終えて1週間後だ。どちらかというと書くのが早い僕にとっては、異例に時間がかかっている。しかも年末進行の真っ最中、ギリギリだった(か、〆切を過ぎていた)と思う。
結果的に、書き上がったものがいいのか悪いのか、今なお僕には分からない。時を経て眺めると、こそばゆくなるような箇所が多々あるし、つい手を出したくなる部分ばかりだ。ただ、「あの日、見たものを書く」という自分の中の目標は、ある程度達成できていると思う。
僕にとっては、大きな意味のある原稿になった。