[和憩団欒房(ブログ)] [参考文献リスト] [資源栞 ( リンク集 )]
[官制大観総目次] [予備知識 総目次][官制の沿革 総目次][官職 総目次]
[役所名50音別索引]
|
|
[トップページ]
[更新のお知らせ ( What's New )]
[和憩団欒房(ブログ)] [参考文献リスト] [資源栞 ( リンク集 )] [官制大観総目次] [予備知識 総目次][官制の沿革 総目次][官職 総目次] [役所名50音別索引] |
− 目次 −
唐代の役人の正式名称は「官人〔かんじん〕」と言います。
「官品〔かんぽん〕」とは、令の官品令に規定されている官人の階級(「品階〔ほんかい〕」)規定を言い、一〜三品までを正・従の二階に、四〜九品までを正・従・上・下の四階に分けた三十階となっています。(ただし、品階を持たない(無品〔むぼん〕の)「官人」もいます。)
この三十階以上に当たる職、すなわち品階を持つ職を「流内官」、それ以下の職を「流外官」と言います。
日本と同様(というか、日本がこちらの制に倣っているのですが)、九品以上の官人には特権が伴います。特に五品以上の官人の特権は多く、これが「貴族」であると言えます。
「官品」には、それぞれの階によって「官名」が決まっており(これは実務を伴う「職名」ではありません)、たとえば、従一品の文官は「開府儀同三司〔かいふぎどうさんし〕」、従一品の武官は「驃騎将軍〔ひょうきしょうぐん〕」などと言います。
こうした特定の官品に相当する官名は「文散官」「武散官」と言い、これによって官人としての階級を示します。
(※日本では「散官」というと、位階だけがあって実務担当職に就いていない人を指して言います。用法が異なりますので注意してください。)
またこの他にも、実務とは関係のない階層規定として「爵」(=王・郡王・国公・郡公・県公・県候・県伯・県子・県男)や「勲官」(=上柱国・柱国・上衛軍・武騎尉など)があります。
※ 「散官」「勲官」「爵」については、予備知識『位階』の「唐の官名との相当」にそれぞれの名を挙げていますので参照ください。
実務のあるもの、つまり「官職」であるものは「職事官〔しきじかん〕」と言います。「職事官」として働いている官人を指しても一般に「職事官」と言っているようです。
「職事官」の勤める役所として、中央には、六省・九寺〔じ〕・一台・五監〔げん〕・十六衛〔えい〕、その他東宮官・親王府官があり、それらの上には「三師」「三公」が立っています(ただし、三師・三公は日本の太政大臣と同様で、常設の職ではなく、特に定められた実務もありません)。
地方には、府・州・県ごとに、そこに属する職があり、また、武官としては折衝府に属する職があります。
これら役所の職には官品との相当規定があります(※後述の「主な職の官品相当」参照)。
「散官」と「職事官」の品階は原則的には相当している筈ですが、場合によって相当していない場合もあります。これも日本と同様です。
役所には、六省・九寺・一台・五監・二十四司・十六衛、その他、五房や東宮官・親王府官があります。
いずれの役所にも「長官」「通判官(次官)」「判官」「主典」の「四部官(四等官・四分官)」の規定があり、立場・責任の所在を分けています(具体的な職名は、役所によって異なります)。
役所のうち、最も上に立っているのが「省」です。国政の中枢で、立案・執行を担当する「尚書省」「中書省」「門下省」の「三省」と、帝に関わる「秘書省」「殿中省」「内侍〔ないじ〕省」の、計「六省」があります。
このうち、「尚書省」は、本庁である「都省」と、「吏部」「戸部」「礼部」「兵部」「刑部」「工部」の「六部」で構成されます。また、尚書省の「長官」は常設の職ではありません。
「六部」の下にはそれぞれ4つずつ、計24の「二十四司(曹)」があり、また「九寺」「五監」もこの下にあります。「都省」の下にも「司」があるようですが、これは調べてないので、よくわかりません。
行政運営は、尚書・中書・門下の三省が中心となります。
中書省が詔勅の起案を行い、門下省がこれを審査し、帝の裁可を経て、尚書省の都省に回し、尚書省の六部がこれを執行します。また、下からの上奏は、尚書省が受理して、中書省が回答文案を作成し、門下省を経て、再び尚書省へ戻されます。
「九寺」の[寺]は、寺院とは無関係な語で[役所]の意です。「太常寺」「光禄寺」「衛尉寺」「宗正寺」「太僕寺」「大理寺」「鴻臚寺」「司農寺」「太府寺」があります。
「五監」は、「国子監」「少府監」「軍器監」「将作監」「都水監」があります。
秦・漢代では、この「九寺」「五監」が中心的な役所でした(個々の名称は時代によって多少異なる場合があります)が、隋・唐では「六部」配下の実務機関として残されました。(伝統的な官庁は根強いので、これを廃止することは、現代日本の行政改革と同様(?)、難しかったようです。)
「台」は「御史台」のことで、これら諸役所の監察を担当します。
以上が行政運営で、政策決定は「政事堂」「中書門下」などという宰相会議で為されます。
「政事堂」の出席者は、「正宰相」である中書省・門下省の長官が各1名(=中書令・門下侍中)と、尚書省の左僕射・右僕射(「長官」ではなく「通判官(次官)」です。時代によって「正宰相」である場合もあります)が各1名、他に宰相待遇を受けている職事官たちです。
政策決定と行政運営は並立しているものだったようですが、中書省・門下省の長官を主とする「政事堂」に実権が移るにつれ、こちらにも独自の配下機関が必要となって、「六部」に相当するような「吏房」「枢機房」「兵房」「戸房」「刑礼房」の「五房」が置かれ、宰相が当直するようになります。
『三公』が、日本に於ける太政大臣・左右大臣に当たる最高官です。
| 隋 | 唐 | 主な担当職務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸侯 | 三師(?) (周代の三公) | 太師 太傅 太保 | 政治の総轄 | |||
| 三公 (後漢以降の三公) | 太尉 | 軍事の審議 | ||||
| 司徒 | 行政の審議 | |||||
| 司空 | 監察の審議 | |||||
| 六省 | 三省 | 〔しょうしょしょう〕 尚書省 | 都省 (本庁) | 令 | 百官の統括・詔勅の施行 | |
| 左僕射〔ぼくや〕 右僕射〔ぼくや〕 | 左丞相〔じょうしょう〕 右丞相〔じょうしょう〕 |
|||||
| 六部 (六官) | 吏部尚書 | 官吏の任免・進退 | ||||
| 民部尚書 | 戸部尚書 | 民事・戸籍・租税 | ||||
| 礼部尚書 | 礼楽・祭祀・外交・教育 | |||||
| 兵部尚書 | 軍事・武官の進退 | |||||
| 刑部尚書 | 刑罰・司法 | |||||
| 工部尚書 | 宮室器物用度・土木 | |||||
| 中書省 | ◆ 内史令 内史侍郎 謁者台大夫 | 諌議大夫 ◆ 中書令 中書侍郎 右散騎常侍 通事舎人 | 詔勅の記録・伝達 | |||
| 門下省 | ◆ 納言 黄門侍郎 | ◆ 侍中〔じちゅう〕 門下侍郎 左散騎常侍 | 詔勅の審査・出納 | |||
| 秘書省 | 令 | |||||
| 殿中省 | 令 | |||||
| 内侍省 | 令 | |||||
| 〔きゅうけい〕 九卿 (=九寺) | 太常寺卿 | 礼楽・祭祀 | ||||
| 光禄寺卿 | 宮殿の内務 | |||||
| 衛尉寺卿 | 宮門の警衛 | |||||
| 太僕寺卿 | 輿馬・行幸の供奉 | |||||
| 大理寺卿 | 刑罰・訟獄 | |||||
| 鴻臚寺卿 | 賓客外交・儀式 | |||||
| 宗正寺卿 | 皇族 | |||||
| 司農寺卿 | 穀物・貨幣 | |||||
| 太府寺卿 | 天子の御料庫 | |||||
| 台官 | 御史台〔ぎょしだい〕大夫 | 官吏の風紀取り締まり | ||||
※ ◆は『宰相』を示しています。京都書房「増補新修国語総覧」を参考に作製。
※ 表中で赤く囲っているのは配下にある「司」の職事官です。
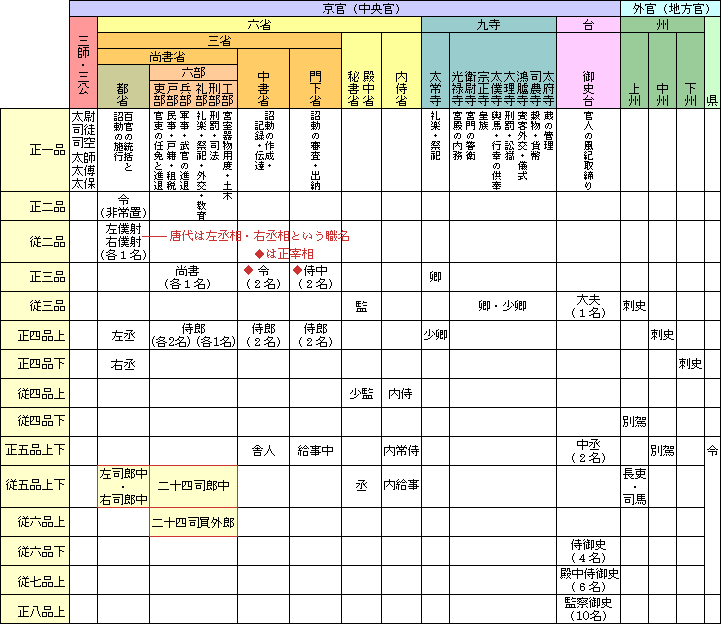
唐の長安城に関して、『予備知識』の「京・宮・みやこ(付:唐の長安城)」で解説していますので、こちらの本文と併せてご参照ください。