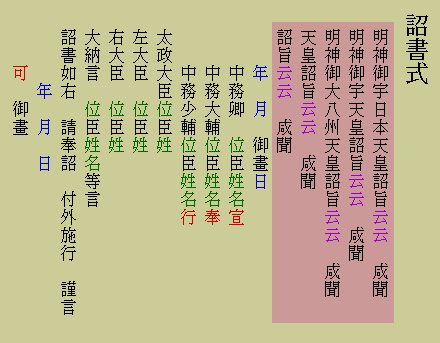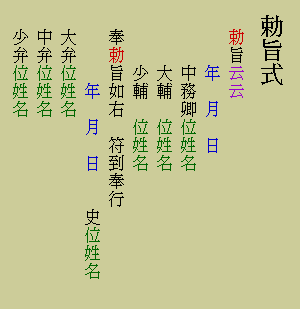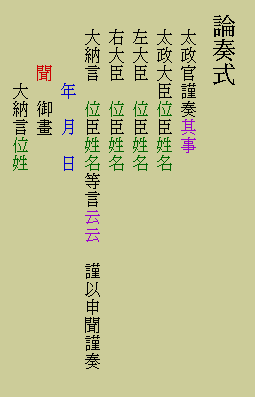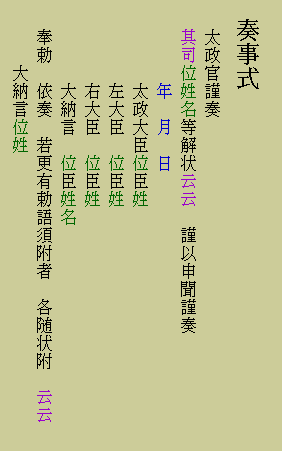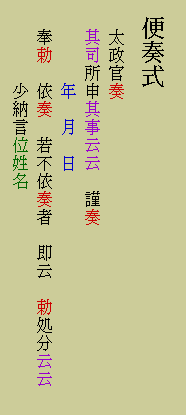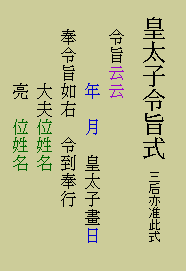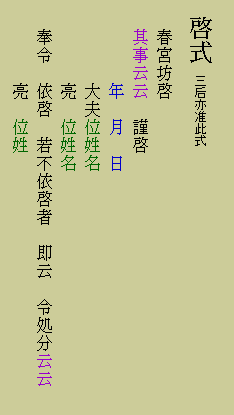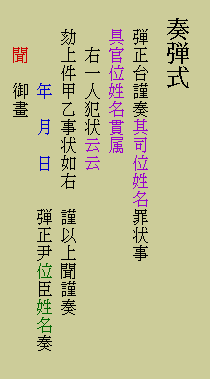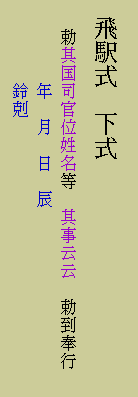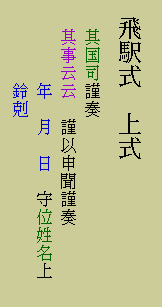付録:現代語訳「養老令」全三十編:
第二十一 公式令 全89条中01〜10条
(最終更新日:00.03.26)
− 目次 −
○01 詔書式条
詔書式(詔下達の公文書様式)
※ 書式
明神御宇日本天皇詔旨云云。咸聞。
明神御宇天皇詔旨云云。咸聞。
明神御大八州天皇詔旨云云。咸聞。
天皇詔旨云云。咸聞。
詔旨云云。咸聞。
年 月 御畫日。
中務卿 位臣姓名宣
中務大輔位臣姓名奉
中務少輔位臣姓名行
太政大臣位臣姓
左大臣 位臣姓
右大臣 位臣姓
大納言 位臣姓名等言。
詔書如右。請奉詔。付外施行。謹言。
年 月 日
可。御畫。
※ 読み
明つ神〔あらみかみ〕とあめのした知らす日本〔ひのもと〕の天皇〔すべら〕が詔旨〔おおんごと〕らまと○○。ことごとくに聞きたまえ。
明つ神とあめのした知らす天皇が詔旨らまと○○。ことごとくに聞きたまえ。
明つ神〔あきつかみ〕と大八州〔おおやしまのくに〕知らす天皇〔すべら〕が詔旨〔おおんごと〕らまと○○。ことごとくに聞きたまえ。
天皇〔すべら〕が詔旨〔おおんごと〕らまと○○。ことごとくに聞きたまえ。
詔旨〔おおんごと〕らまと○○。ことごとくに聞きたまえ。
年 月 御〔ご〕、日〔にち〕畫〔か〕いたまう。
中務卿 位臣姓名が宣〔せん〕
中務大輔位臣姓名が奉〔ぶう〕
中務少輔位臣姓名が行〔ぎょう〕
太政大臣位臣姓
左大臣 位臣姓
右大臣 位臣姓
大納言 位臣姓名等〔ら〕言〔もう〕すこと。
詔書〔おおんごと〕らま右の如し。請〔うけたまわ〕らくは詔〔じょう〕を奉〔うけたまわ〕りて、外〔げ〕に付〔さず〕けて施行〔せぎょう〕せむと。謹〔かしこ〕む言〔もう〕す。
年 月 日
可。御、畫いたまう。
※ 訳
現神として天下をお治めになる日本天皇の詔の旨は、○○。ことごとくにお聞きください。
現神として天下をお治めになる天皇の詔の旨は、○○。ことごとくにお聞きください。
現神として大八州をお治めになる天皇の詔の旨は、○○。ことごとくにお聞きください。
天皇の詔の旨は、○○。ことごとくにお聞きください。
詔の旨は、○○。ことごとくにお聞きください。
詔本文の起草日付(年月)≪天皇(日付)ご記入箇所≫日。
中務卿 位臣姓名(=中務卿の位署)が宣す(代わって詔を下す)
中務大輔位臣姓名(=中務大輔の位署)が奉る(うけたまわる)
中務少輔位臣姓名(=中務少輔の位署)が行う(太政官に送付する)
太政大臣位臣姓(=太政大臣の位署)
左大臣 位臣姓(=左大臣の位署)
右大臣 位臣姓(=右大臣の位署)
大納言 位臣姓名(=大納言の位署)等〔ら〕(このように)申すこと。
詔書は右のとおり。願わくば詔をうけたまわって、外(=諸司)に授けて施行しようと存じます。かしこみ申し上げます。
この文書の覆奏日付(年月日)
可。≪天皇(裁可)ご記入箇所≫
右は、御画日〔ごえにち〕までの正文を中務省に留めて案(保管文書)とすること。別に1通を写して印署(内印を捺し、中務卿〜少輔が署名)して、太政官に送ること。大納言は覆奏すること。天皇が「可」とお書きになることが終わったならば、留めて案とすること。さらに1通写して(詔書として)通告すること。終わったならば施行すること。中務卿がもし不在ならば、大輔の姓名の下に「宣」と記すこと。少輔の姓名の下に「奉行」と記すこと。大輔もまた不在の場合は、少輔の姓名の下に併せて「宣奉行」と記すこと。もし少輔が不在ならば、その他の太政官の役人の現在いる人で、いずれもこれに準じること。
○02 勅旨式条
勅旨式(勅下達の公文書様式)
※ 書式
勅旨云云。
年 月 日
中務卿位姓名
大輔 位姓名
少輔 位姓名
奉勅旨如右。符到奉行。
年 月 日 史位姓名
大弁位姓名
中弁位姓名
少弁位姓名
※ 読み
勅旨は、○○。
年 月 日
中務卿位姓名
大輔 位姓名
少輔 位姓名
勅旨〔ちょくし〕奉〔うけたまわれ〕れること右の如し。符〔ふ〕到らば奉〔うけたまわ〕り行え。
年 月 日 史位姓名
大弁位姓名
中弁位姓名
少弁位姓名
※ 訳
勅旨は、○○。
この草案の覆奏日付(年月日)
中務卿位姓名(=中務卿の位署)
大輔 位姓名(=中務大輔の位署)
少輔 位姓名(=中務少輔の位署)
うけたまわった勅旨は右のとおり。太政官符が到着したならば、うけたまわり施行すること。
起草日付(年月日) 史位姓名(=起草者である史の位署)
大弁位姓名(=弁の位署)
中弁位姓名( 〃 )
少弁位姓名( 〃 )
右は、勅をうけたまわった人が、中務省に宣送すること。中務は(施行許可を求めて)覆奏すること。終わったならばこの書式に依って署名を取ること。留めて案とすること。さらに1通写して太政官に送ること。少弁以上はこの書式に依って連署すること。留めて案とすること。さらに1通写して施行すること。(直接下達の)勅で五衛府(衛門・左右衛士・左右兵衛)及び兵庫(左右兵庫・内兵庫)のことを処分する場合、本司(五衛府・兵庫の諸司)が覆奏すること。皇太子が監国〔けんごく〕(天皇が出行して皇太子が留守番をすること)する場合も、またこの書式に準じること。令を以て勅に代えること。
○03 論奏式条
論奏式(論奏=太政官が天皇に上奏して裁可を求める公文書の様式)
※ 書式
太政官謹奏其事
太政大臣位臣姓名
左大臣 位臣姓名
右大臣 位臣姓名
大納言 位臣姓名等言云云。謹以申聞謹奏。
年 月 日
聞。御畫。
大納言位姓
※ 読み
太政官謹〔かしこ〕む奏〔もう〕す、○○
太政大臣位臣姓名
左大臣 位臣姓名
右大臣 位臣姓名
大納言 位臣姓名等言〔もう〕す、○○。謹〔かしこ〕み以〔かしこ〕みも申したまうことを聞〔きこ〕しめせと謹〔かしこ〕む奏〔もう〕す。
年 月 日
聞。御、畫きたまう。
大納言位姓
※ 訳
太政官より、かしこみ申し上げます、○○の事について
太政大臣位臣姓名(=議政官である太政官の位署)
左大臣 位臣姓名(= 〃 )
右大臣 位臣姓名(= 〃 )
大納言 位臣姓名(= 〃 )等〔ら〕が申し上げます、○○(主本文)。かしこみかしこみも申し上げることをお聞き届けくださいますようかしこみ申し上げます。
論奏日付(年月日)
聞。≪天皇(裁可)記入箇所≫
大納言位姓(=奏官(奏上者)の位署)
右は、大祭祀のとき、国家予算の立案、官員の増減、流罪以上及び除名の処断、国郡の廃置、兵馬100匹以上の徴発、蔵の収納物500端以上・銭200貫以上・倉粮(民部の倉廩や諸国正倉などの米・糒〔ほしいい〕)500石以上・奴婢20人以上・馬50匹以上・牛50頭以上の臨時予算の計上、勅授以外に五位以上を授ける場合、及び、律令以外に会議をして奏す場合に、いずれも論奏として作成すること。天皇が「聞」とお書きになることが終わったならば、留めて案とすること。御画〔ごえ〕の後に奏官(大納言)の位姓を記すこと。
○04 奏事式条
奏事式(奏事=諸司の解状を得て、太政官が天皇に上奏する公文書の様式)
※ 書式
太政官謹奏
其司位姓名等解状云云。謹以申聞謹奏。
年 月 日
太政大臣位臣姓
左大臣 位臣姓
右大臣 位臣姓
大納言 位臣姓名
奉勅。依奏。若更有勅語須附者。各随状附。云云。
大納言位姓
※ 読み
太政官謹〔かしこ〕む奏〔もう〕す
△△司位姓名等解状○○。謹〔かしこ〕み以〔かしこ〕みも申したまうことを聞〔きこ〕しめせと謹〔かしこ〕む奏〔もう〕す。
年 月 日
太政大臣位臣姓
左大臣 位臣姓
右大臣 位臣姓
大納言 位臣姓名
勅〔ちょく〕奉〔うけたまわ〕るに、奏〔そう〕に依りぬと言え。若し更に勅語有りて附くべくは、各〔おのおの〕状に随いて附けて、○○と言え。
大納言位姓
※ 訳
太政官より、かしこみ申し上げます
△△司の位姓名等の解状により○○。かしこみかしこみも申し上げることをお聞き届けくださいますようかしこみ申し上げます。
奏事日付(年月日)
太政大臣位臣姓(=議政官である太政官の位署)
左大臣 位臣姓(= 〃 )
右大臣 位臣姓(= 〃 )
大納言 位臣姓名(= 〃 )
(承認の)勅を奉〔うけたまわ〕ったなら、奏聞〔そうもん〕の結果である、と言うこと。もしここで更に勅語があって追加する場合は、状況に応じて追加して、○○と言うこと。
大納言位姓(=奏官(奏上者)の位署)
右は、論奏以外に諸々のことを奏す場合は、いずれも奏事として作成すること。みな案が完成したなら奏すること。奉勅の後に奏官(大納言)の位姓を記すこと。もし少納言が奏したならば、名を加えること。
○05 便奏式条
便奏式(便奏=諸司の解状等を得て、太政官が天皇に上奏する公文書の様式)
※ 書式
太政官奏
其司所申其事云云。謹奏。
年 月 日
奉勅。依奏。若不依奏者。即云。勅処分云云。
少納言位姓名
※ 読み
太政官奏〔もう〕す
△△司の申す所の○○の事、○○。謹〔かしこ〕み奏〔もう〕す。
年 月 日
勅〔ちょく〕奉〔うけたまわ〕るに、奏〔そう〕に依りぬと言え。若し奏に依らずは即ち云わまく、勅の処分○○と言え。
少納言位姓名
※ 訳
太政官より、申し上げます
△△司の申す所の○○の事、○○。かしこみ申し上げます。
便奏日付(年月日)
(承認の)勅を奉〔うけたまわ〕ったなら、奏聞〔そうもん〕の結果である、と言うこと。もし奏聞を承認されたのでない場合、勅の処分は○○であると言うこと。
少納言位姓名(=奏官(奏上者)の位署)
右は、鈴印を請けたてまつるとき、及び、衣服・塩酒・菓食を賜るとき、併せて医薬の給付、こうした小事の類は、いずれも便奏として作成すること。口頭で奏する場合は、いずれもこの例に準じること。奉勅の後に、奏官(少納言)の位姓名を記すこと。皇太子が監国する場合もまたこの書式に準じて、奏・勅の字を啓・令に置き代えること。
○06 令旨式条
皇太子令旨式(令旨下達の公文書様式){三后もまたこの書式に準じること。}
※ 書式
令旨云云。
年 月 皇太子畫日。
奉令旨如右。令到奉行。
大夫位姓名
亮 位姓名
※ 読み
令旨〔りょうじ〕○○。
年 月 皇太子、日畫いたまう。
令旨奉〔うけたまわ〕ること右の如し。令〔りょう〕到らば奉〔うけたまわ〕り行え。
大夫位姓名
亮 位姓名
※ 訳
令旨〔りょうじ〕は○○。
年 月 ≪皇太子(日付)ご記入箇所≫
うけたまわった令旨は右のとおり。令が到着したならば、うけたまわり施行すること。
大夫位姓名(=春宮坊長官の位署)
亮 位姓名(= 〃 次官の位署)
右は、令をうけたまわった人が、春宮坊に宣送すること。春宮坊は(施行許可を求めて)覆啓すること。終わったならば、画日までの正文を留めて案とすること。さらに一通写して施行すること。
○07 啓式条
啓式(春宮坊の発議案件に皇太子の承認を求める公文書様式){三后もまたこの書式に準じること。}
※ 書式
春宮坊啓
其事云云。謹啓。
年 月 日
大夫位姓名
亮 位姓名
奉令。依啓。若不依啓者。即云。令処分云云。
亮 位姓
※ 読み
春宮坊啓〔けい〕す
○○の事、○○。謹〔かしこ〕み啓す。
年 月 日
大夫位姓名
亮 位姓名
令〔りょう〕奉〔うけたまわ〕るに、啓〔けい〕に依りぬと言え。若し啓に依らずは即ち云わまく、令の処分○○と言え。
亮 位姓
※ 訳
春宮坊より申し上げます
○○の事、○○。かしこみ申し上げます。
上啓日付(年月日)
大夫位姓名(=春宮坊長官の位署)
亮 位姓名(= 〃 次官の位署)
令〔りょう〕を奉〔うけたまわ〕ったなら、啓〔けい〕の結果である、と言うこと。もし啓を承認されたのでない場合、令の処分は○○であると言うこと。
亮 位姓(=啓官(上啓者)の位署)
右は、春宮坊の啓式。奉令の後に、啓官の位姓を記すこと。
○08 奏弾式条
奏弾式(弾正台が天皇に直接奏上する非違摘発の公文書様式)
※ 書式
弾正台謹奏其司位姓名罪状事
具官位姓名貫属
右一人犯状云云。
劾上件甲乙事状如右。謹以上聞謹奏。
年 月 日 弾正尹位臣姓名奏
聞。御畫。
※ 読み
弾正台謹〔かしこ〕む奏〔もう〕す△△司位姓名が罪状の事
具官〔ぐかん〕位〔い〕姓名〔しょうみょう〕貫属〔かんぞく〕
右は一人の犯状〔ぼんじょう〕○○と言え。
上が件〔くだり〕の甲乙〔こういち〕劾〔と〕うこと、事状〔じじょう〕右の如し。謹〔かしこ〕む以〔かしこ〕むも上聞〔もう〕したまうと謹〔かしこ〕む奏〔もう〕す。
年 月 日 弾正尹位臣姓名が奏
聞。御、畫きたまう。
※ 訳
弾正台より、かしこみ申し上げます △△司の○○(位姓名)の罪状の事
△△官・○○位・姓・名・本籍地(=非摘発者)
右の一人の罪状は○○。
上の件の犯罪の当否を弾劾すること、事状は右の通り。かしこむかしこむも申し上げますとかしこむ申し上げます。
年 月 日 弾正尹位臣姓名(=奏官(奏上者)である弾正尹の位署)が奏上
聞。≪天皇(了承)記入箇所≫
右は、親王及び五位以上{太政大臣はこの範囲にない}に違犯があって、弾劾・糺弾する場合に、実情を明らかにしてないときは状況に応じて勘問すること。拷問して取り調べてはならない。委細に事の由を知ること。事が大であれば奏弾すること。終わったならば、弾正台に留めて案とすること。奏すにあたらない場合、及び六位以下は、いずれも糺弾して所司(担当の司=刑部省・左右京職)に移して、推判すること。
○09 飛駅式条
飛駅式(飛駅発遣時の公文書様式)
下式(飛駅による勅命下達の公文書様式)
※ 書式
勅其国司官位姓名等。其事云云。勅到奉行。
年 月 日 辰
鈴剋
※ 読み
勅す、△△国の△△司○○(官位姓名)等に。○○の事○○。勅到らば奉〔うけたまわ〕り行え。
年 月 日 辰〔とき〕
鈴剋〔すずきざみ〕
※ 訳
勅命を下す、△△国の△△司○○(官位姓名)等に。○○の事は○○。勅符が到着したならば奉〔うけたまわ〕り行うこと。
飛駅発遣日付(年月日時刻)
鈴剋(飛駅使に与えられる駅鈴の刻数)
○10 飛駅上式条
上式(飛駅による在外諸司からの上申の公文書様式)
※ 書式
其国司謹奏
其事云云。謹以申聞謹奏。
年 月 日 守位姓名上
鈴剋
※ 読み
△△国の司謹〔かしこ〕む奏〔もう〕す
○○の事○○。謹〔かしこ〕み以〔かしこ〕みも申聞〔もう〕したまうと謹〔かしこ〕み奏〔もう〕す。
年 月 日 守位姓名上〔たてまつ〕る
鈴剋〔すずきざみ〕
※ 訳
△△国の司より、かしこみ申し上げます
○○の事○○。かしこみかしこみも申し上げますとかしこみ申し上げます。
飛駅発遣日付(年月日) 守位姓名(=国守(長官)の位署)が上申します
鈴剋(飛駅使に与えられる駅鈴の刻数)
右の、飛駅〔ひやく〕(緊急時に発する中央と在外諸司・軍所との連絡使節)の上申下達する書式は、もし長官不在のときは、次官以下が、この書式に依って署名すること。国司ではなく、別に軍所から上奏する場合は、副将軍以上がいずれも署名すること。{大宰府もこれに準じること。}
[養老各令の概説]
[令条全索引]
[現代語訳「養老令」凡例他]
[官位令]
[職員令(01〜20)]
[職員令(21〜38)]
[職員令(39〜57)]
[職員令(58〜80)]
[後宮職員令]
[東宮職員令]
[家令職員令]
[神祇令]
[僧尼令]
[戸令(01〜22)]
[戸令(23〜45)]
[田令(01〜19)]
[田令(20〜37)]
[賦役令(01〜14)]
[賦役令(15〜39)]
[学令]
[選叙令(01〜19)]
[選叙令(20〜38)]
[継嗣令]
[考課令(01〜49)]
[考課令(50〜75)]
[禄令]
[宮衛令]
[軍防令(01〜23)]
[軍防令(24〜51)]
[軍防令(52〜76)]
[儀制令]
[衣服令]
[営繕令]
[公式令(01〜10)]
[公式令(11〜22)]
[公式令(23〜61)]
[公式令(62〜89)]
[倉庫令]
[廐牧令]
[医疾令]
[假寧令]
[喪葬令]
[関市令]
[捕亡令]
[獄令(01〜20)]
[獄令(21〜42)]
[獄令(43〜63)]
[雑令(01〜21)]
[雑令(22〜41)]
[現代語訳「養老令」全三十編]
[官制大観総目次][予備知識 総目次][官制の沿革 総目次][官職 総目次]
[役所名50音別索引]
[トップページ]
[更新のお知らせ ( What's New )]
[和憩団欒房(ブログ)]
[参考文献リスト]
[資源栞 ( リンク集 )]
© 1997-2010 MinShig All Rights Reserved.