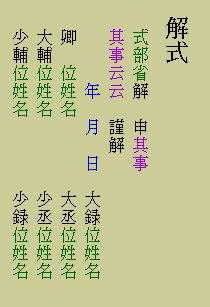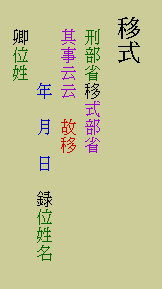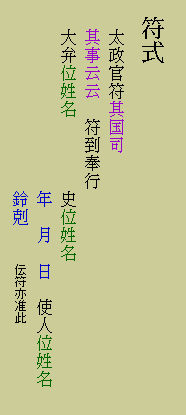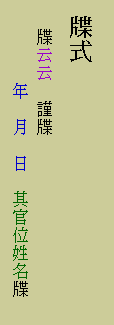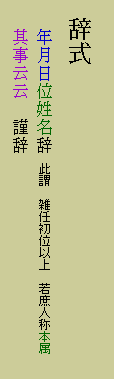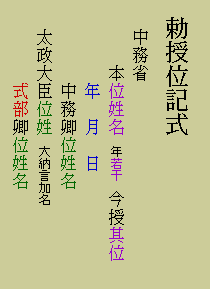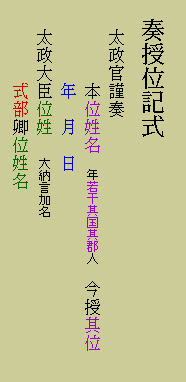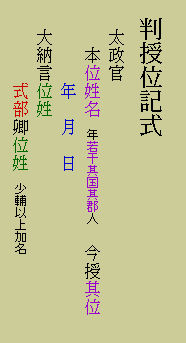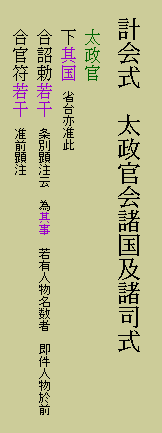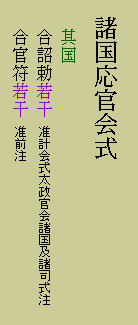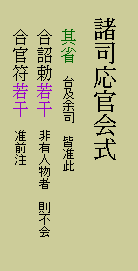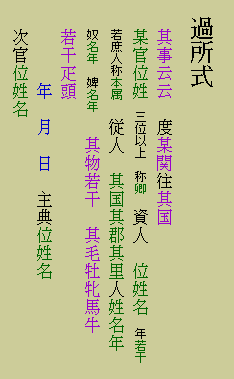付録:現代語訳「養老令」全三十編:
第二十一 公式令 全89条中11〜22条
(最終更新日:00.03.26)
− 目次 −
○11 解式条
解式(被管の下級官司が所管の上級官司に上申する公文書様式)
※ 書式
式部省解 申其事
其事云云。謹解。
年 月 日 大録位姓名
卿 位姓名 大丞位姓名
大輔位姓名 少丞位姓名
少輔位姓名 少録位姓名
※ 読み
式部省解し 申す○○の事
○○の事○○。謹解〔きんげ〕。
年 月 日 大録位姓名
卿 位姓名 大丞位姓名
大輔位姓名 少丞位姓名
少輔位姓名 少録位姓名
※ 訳
式部省より解(=上申)し 申します○○の事について(=事書き)
○○の事は○○。謹んで解〔げ〕します。
発行日付(年月日) 大録位姓名(=この文案を考え記した作成責任者である三等官(サカン)の位署)
卿 位姓名 大丞位姓名(=送信側の四部官(四等官・四分官)全員の位署)
大輔位姓名 少丞位姓名
少輔位姓名 少録位姓名
右は、八省以下の内外(=京内・京外)の諸司が、太政官、及び、管轄する上級官司に上申する場合に、いずれも解として作成すること。太政官に向けたものでなければ、「以」の字を以て「謹」の字に代えること。
○12 移式条
移式(直接の上下関係にない官司相互で伝達する公文書様式)
※ 書式
刑部省移式部省
其事云云。故移。
年 月 日 録位姓名
卿位姓
※ 読み
刑部省移〔い〕す式部省に
○○の事○○。故移〔こい〕。
年 月 日 録位姓名
卿位姓
※ 訳
刑部省より、移す 式部省に
○○の事は○○。ゆえに移す。
発行日付(年月日) 録位姓名(=この文案を考え記した作成責任者であるサカンの位署)
卿位姓(=送信側の長官の位署)
右は、八省が互いに移(=伝達)する書式。内外(=京内・京外)の諸司で互いに管隷(統属)してない場合は、いずれも移として作成すること。もし事情に応じて管隷の関係にあたる場合(文官から考課のことなどで式部に文書を送るときなど)は、「以」の字を以て「故」の字に代えること。長官の署名にあたっては卿に準じること。{長官不在のときは、次官、判官が署名すること。}国司もまたこれに準じること。僧綱が諸司と互いに報答する場合もまたこの書式に準じること。「移」の字を「牒」の字に代えること。署名については省に準じること。{三綱もまた同じ。}
○13 符式条
符式(所管の上級官司から被管の下級官司へ下達する公文書様式)
※ 書式
太政官符其国司
其事云云。符到奉行。
大弁位姓名 史位姓名
年 月 日 使人位姓名
鈴剋{伝符もまたこれに準じること。}
※ 読み
太政官符△△国の司に
○○の事○○。符到らば奉行〔ぶうぎょう〕せよ。
大弁位姓名 史位姓名
年 月 日 使人位姓名
鈴剋{伝符(伝馬を利用する使者に与えられる証)もまたこれに準じること。}
※ 訳
太政官符△△国の司に
○○の事は○○。符が到着したならば実施すること。
大弁位姓名 史位姓名(=作成にあたった弁と史の位署)
発行日付(年月日) 使人位姓名(=符を送達する使者)
鈴剋(使者に与えられる駅鈴(や伝符)の数量)
右は、太政官が国に下す符式。{省・台もこれに準じること。}もし在京の諸司に下す場合は、使人より以下は記さない。解によって上申する関係にある官司の間で、上官(上級官司)から下級官司に向ける場合には、みな符として作成すること。(省・台の)署名については、この例文の弁官に準じること(長官と主典が位署する)。(省・台からの)出符(実際に発布する符)はみな、草案(発布する符の原稿である本案)が完成するのを待って、出符と草案とを併せて太政官に送って検句すること。{もし事を計会〔けいえ〕(公文書の相互対照・確認)すべき場合は、会目〔えもく〕(計会する符を記した目録)を記録して、符とともに太政官に送ること。}
○14 牒式条
牒式(内外の四部官(四等官・四分官)以上の個人が諸司に上申する公文書の様式)
※ 書式
牒云云。謹牒。
年 月 日 其官位姓名牒
※ 読み
牒〔ぢょう/ちょう〕○○。謹牒〔きんぢょう/きんちょう〕。
年 月 日 △△官位姓名が牒
※ 訳
牒○○。謹んで牒します。
発行日付(年月日) △△官位姓名が牒します
右は、内外の主典以上の官人が、事情があって諸司に申牒〔しんちょう/しんぢょう〕(=上申)するときの書式。{三位以上は名を除くこと。}もし人と物の名前・数量がある場合、人と物を(牒云云の)前に挙げて箇条書きすること。
○15 辞式条
辞式(内外の雑任以下の個人が諸司に上申する公文書の様式)
※ 書式
年月日位姓名辞。{ここは雑任の初位以上をいう。もし庶人であれば本籍を称すること。}
其事云云。謹辞。
※ 読み
年月日位姓名が辞。{ここは雑任の初位以上をいう。もし庶人であれば本籍を称すること。}
○○の事○○。謹辞〔きんじ〕。
※ 訳
発行日付(年月日)位姓名が辞。{この例は雑任の初位以上の場合。もし庶人であれば本籍を称すること。}
○○の事○○。謹んで辞します。
右は、内外の雑任以下が、諸司に申牒〔しんちょう/しんぢょう〕(=上申)するときの書式。もし人と物の名前・数量があれば、人と物を云云の前に挙げて箇条書きすること。
○16 勅授位記式条
勅授の位記式(内外五位以上の位記の書式)
※ 書式
中務省
本位姓名{年若干}今授其位
年 月 日
中務卿位姓名
太政大臣位姓{大納言は名を加えること。}
式部卿位姓名
※ 読み
中務省
本〔もと〕の位姓名{年若干}今授けたまう○位
年 月 日
中務卿位姓名
太政大臣位姓{大納言は名を加えること。}
式部卿位姓名
※ 訳
中務省(=天皇の意志を受けて位記の案作成を担当)
もとの位姓名{年○○}に、いま○位(=新しく叙す位階)をお授けになる
発行日付(年月日)
中務卿位姓名(=位記案作成担当官司の長官としての位署)
太政大臣位姓(=位記交付を担当する太政官の長官のみの位署){大臣に支障がある場合には大納言が名を加えること。}
式部卿位姓名(=文官の考課を担当する官司の長官としての位署。武官の場合は兵部省)
右は、勅で五位以上の位記をお授けになるときの書式。みな在任の(太政官・中務・式部の)長官一人が署名すること。もし長官が不在ならば、大納言及び少輔以上が書式に依って署名すること。{兵部もまた同じ。以下もこれに準じること。}
○17 奏授位記式条
奏授の位記式(内外六位以下〜内八位・外七位までの位記の書式)
※ 書式
太政官謹奏
本位姓名{年若干其国其郡人}今授其位
年 月 日
太政大臣位姓{大納言は名を加えること。}
式部卿位姓名
※ 読み
太政官謹奏〔きんそう〕
本〔もと〕の位姓名{年○○△△国△△郡の人}今授けたまう○位
年 月 日
太政大臣位姓{大納言は名を加えること。}
式部卿位姓名
※ 訳
太政官(=位記案作成の主体)謹んで奏します
もとの位姓名{年○○△△国△△郡の人}に、いま○位(=新しく叙す位階)をお授けになる
発行日付(年月日)
太政大臣位姓(=位記作成・交付を担当する太政官の長官のみの位署){大納言は名を加えること。}
式部卿位姓名(=文官の考課を担当する官司の長官としての位署。武官の場合は兵部省)
右は、奏して六位以下の位記をお授けになるときの書式。
○18 判授位記式条
判授の位記式(外八位と内外初位の位記の書式)
※ 書式
太政官
本位姓名{年若干其国其郡人}今授其位
年 月 日
大納言位姓
式部卿位姓{少輔以上は名を加えること。}
※ 読み
太政官
本の位姓名{年○○△△国△△郡の人}今授けたまう○位
年 月 日
大納言位姓
式部卿位姓{少輔以上は名を加えること。}
※ 訳
太政官(=式部・兵部の案を検討して位記の交付を担当)
本の位姓名{年○○△△国△△郡の人}に、いま○位(=新しく叙す位階)をお授けになる
発行日付(年月日)
大納言位姓(=位記作成・交付を担当する太政官の担当官としての位署)
式部卿位姓(=文官の考課を担当する官司の長官としての位署。武官の場合は兵部省){少輔以上は名を加えること。}
右は、判って、外八位、及び、内外の初位の位記をお授けになるときの書式。
○19 計会式条
計会〔けいえ〕式(計会帳(=官司間が授受・交換した公文書や人員・物件を相互に照会するための帳簿)の書式)
太政官が諸国及び諸司に会〔え〕する式(太政官が年間に下した公文書を諸国・諸司別に集計する、計会のための帳簿(=会)の書式)
※ 書式
太政官
下其国。{省・台もまたこれに準じること。}
合詔勅若干{条別にし、明記して「為其事」と記載すること。もし人と物の名前・数量があれば、人と物を前に挙げて箇条書きすること。}
合官符若干{前に準じて明記すること。}
※ 読み
太政官
下す△△国に。{省・台もまたこれに準じること。}
合せて詔勅○○{条別にし、明記して「為○○の事」と記載すること。もし人と物の名前・数量があれば、人と物を前に挙げて箇条書きすること。}
合せて官符○○{前に準じて明記すること。}
※ 訳
太政官
下す△△国に。{省・台に下した場合もまたこれに準じること。}
詔勅の合計○○(=年間にその国・司に下した詔勅の条数){条別にし、明記して「○○(=内容の要約)の事の為」と記載すること。もし人と物の名前・数量があれば、人と物を「○○(=内容の要約)の事の為」の前に挙げて箇条書きすること。}
官符の合計○○(=年間にその国・司に下した官符の条数){前に準じて明記すること。}
右は、追(在外の人の召喚)徴(国司の欠員の徴発)科造(造作命令)するとき、人や物を送り納めるとき{物とは官物のことをいう。人とは流人を流し徒人を移すこと、及び、逃亡者を捕獲する類をいう。}、除附(除籍・附籍)・【益蜀】免〔げんめん〕(【益蜀】符による課役免除)のとき、及び、解官するとき、位記を追徴(剥奪)するときに、みな諸国・諸司の種類別に会〔え〕(公文書)を作成して、計会帳に「某年月日下国某符、其月日付使人某官位姓名(作成×年×月×日付で国に下した○○符、×月×日付で使人△△官位姓名に渡したもの)」と記載すること。{もし返抄〔へんじょう〕(国司等が太政官に提出する受領証)を得ていたならば、「得其官位姓名某月日返抄(△△官位姓名の×月×日付の返抄を得ている)」と記載すること。}(この書式は太政官が下した公文書の場合であるが、)もし太政官の処分ではなく、国司が人や物を京及び他国に向けて送った場合には、送った所も受領した所も、またこれに準じて会を作成すること。
○20 諸国会式条
諸国が太政官に会すべき式(諸国が年間の公文書を集計し太政官へ提出する、計会のための帳簿(=会)の書式)
※ 書式
其国
合詔勅若干{前に準じて記すこと。}
合官符若干{前に準じて記すこと。}
※ 読み
△△国
合せて詔勅○○{前に準じて記すこと。}
合せて官符○○{前に準じて記すこと。}
※ 訳
△△国
詔勅の合計○○(=年間にその国が受領した詔勅の条数){前に準じて記すこと。}
官符の合計○○(=年間にその国が受領した官符の条数){前に準じて記すこと。}
右は、計会帳に「被官其年月日符下。追徴科造等事。其符其月日到国。依符送其処訖。獲其位姓名其月日返抄。(太政官の×年×月×日付で下した符による追徴科造などの事を受け取った。その符は×月×日に国に到着し、符に依って命じられた処△△に送り終わり、○位姓名の×月×日付の返抄を得ている)」と記載すること。受納の司もまた、実際に受領した数に依って会を作成すること。もし両国が相互に送付・受領する場合はまた、これに準じて会を作成して太政官に送り、照らし合わせて監査すること。
○21 諸司会式条
諸司が太政官に会すべき式(諸司が年間の公文書を集計し太政官へ提出する、計会のための帳簿(=会)の書式)
※ 書式
其省{弾正台、及びその他の司もみなこれに準じること。}
合詔勅若干{人や物があるわけでない場合は会さない。}
合官符若干{前に準じて記すこと。}
※ 読み
△△省{弾正台、及びその他の司もみなこれに準じること。}
合せて詔勅○○{人や物があるわけでない場合は会さない。}
合せて官符○○{前に準じて記すこと。}
※ 訳
△△省{弾正台、及びその他の司もみなこれに準じること。}
詔勅の合計○○(=年間にその司が受領した詔勅の条数){人員や物品の授受がない場合は照会しない。}
官符の合計○○(=年間にその司が受領した官符の条数){前に準じて記すこと。}
右は、計会帳に「被官其年月日符令納。其月日得其国解送。依数納訖。(太政官の×年×月×日付の符による受納命令を受け取った。×月×日付で△△国の解送(下から上への送付)を得て、数量どおり受納を終えた。)」と記載すること。
前年度の会〔え〕(=照会)すべき事柄は、7月30日以前までをもって区切りとすること。12月の上旬に監査を終えること。{被管(管理される側)の諸司はみな、所管(管理する側)において監査すること。その他の諸司(よそと統属関係がない官司)はそれぞれ本司(自分のところ)で審査すること。いずれも漏らすことのないようにし、然る後に長官が押署(署名捺印)して、封をして太政官に送ること。国司もまたこれに準じること。}朝集使に預けて太政官に送ること。少弁及び史等を分配派遣して、諸司の主典及び朝集使を全て集め、対勘(対面して口頭審問)すること。もし詐偽隠漏(故意の偽りや隠し漏れ)があって不同があったならば、状態に応じて推問追求すること。過失で脱漏があって考に付けるときは、五分(まで(?))をもって論じること。一分漏らすごとに考を一等降すこと。被管の考を通計して所管の考とすること。弁官はそれを箇条書きに記録して式部省(ないしは兵部省)に送り、考に付けて(本人に)唱示すること。照会すべきもの(追徴科造等)以外で(太政官と(?))公文書を授受すべき場合で、在京の諸司なら1ヶ月以内に報告しなかったとき、諸国なら行程の期間を計算外として一季(3ヶ月)以内に報告が行われなかったときには、毎年、朝集使の来た日に、いずれも記録して省(式部/兵部)に送ること。対面して唱示して考に付けること。
○22 過所式条
過所式(過所(=関の通行許可書)の書式)
※ 書式
其事云云。度某関往其国。
某官位姓。{三位以上は卿称する(姓の後に卿と付ける)こと。}資人。位姓名。{年若干。庶人の場合は本籍を書くこと。}従人。某国某郡某里人姓名年。{奴の名年。婢の名年。}其物若干。其毛牡牝馬牛若干疋頭。
年 月 日 主典位姓名
次官位姓名
※ 読み
○○の事○○。△△の関を度〔こ〕え、△△国に往くと言え。
△△官位姓。{三位以上は卿称する(姓の後に卿と付ける)こと。}資人。位姓名。{年○○。庶人の場合は本籍を書くこと。}従人。△△国△△郡△△里の人姓名年。{奴の名年。婢の名年。}××の物○○。××の毛の牡牝の馬牛○○疋頭。
年 月 日 主典位姓名
次官位姓名
※ 訳
○○の事○○。(過所の申請事由)△△の関を越え、△△国(=目的地)に往く、と記述すること。
△△官位姓。(=申請者){三位以上は卿称する(姓の後に卿と付ける)こと。}資人。位姓名。{年○○。庶人の場合は本籍を書くこと。}従人。△△国△△郡△△里の人姓名年。{奴の名年。婢の名年。}××の物(=携行物)○○(数量)。××(毛色)の毛の牡牝の馬牛○○(数量)疋頭。
発行日付(年月日) 主典位姓名(=過所を発行する官司の三等官)
次官位姓名(=過所を発行する官司の次官)
右の過所(関の通行許可書)の書式は、いずれもここで例示した書式に依ってつぶさに2通記録し、所司(過所発行を担当する役所。在京の人なら左右京職、在外の人なら国など)に申請させること。所司は監査して同意したならば、すぐに書式に依って署名すること。1通は留めて案とすること。1通は申請者に判給(=発給)すること。
[養老各令の概説]
[令条全索引]
[現代語訳「養老令」凡例他]
[官位令]
[職員令(01〜20)]
[職員令(21〜38)]
[職員令(39〜57)]
[職員令(58〜80)]
[後宮職員令]
[東宮職員令]
[家令職員令]
[神祇令]
[僧尼令]
[戸令(01〜22)]
[戸令(23〜45)]
[田令(01〜19)]
[田令(20〜37)]
[賦役令(01〜14)]
[賦役令(15〜39)]
[学令]
[選叙令(01〜19)]
[選叙令(20〜38)]
[継嗣令]
[考課令(01〜49)]
[考課令(50〜75)]
[禄令]
[宮衛令]
[軍防令(01〜23)]
[軍防令(24〜51)]
[軍防令(52〜76)]
[儀制令]
[衣服令]
[営繕令]
[公式令(01〜10)]
[公式令(11〜22)]
[公式令(23〜61)]
[公式令(62〜89)]
[倉庫令]
[廐牧令]
[医疾令]
[假寧令]
[喪葬令]
[関市令]
[捕亡令]
[獄令(01〜20)]
[獄令(21〜42)]
[獄令(43〜63)]
[雑令(01〜21)]
[雑令(22〜41)]
[現代語訳「養老令」全三十編]
[官制大観総目次][予備知識 総目次][官制の沿革 総目次][官職 総目次]
[役所名50音別索引]
[トップページ]
[更新のお知らせ ( What's New )]
[和憩団欒房(ブログ)]
[参考文献リスト]
[資源栞 ( リンク集 )]
© 1997-2010 MinShig All Rights Reserved.